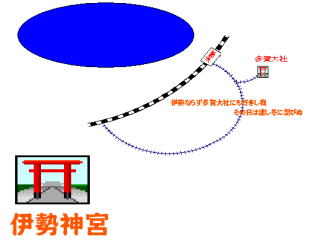| <<前のページ | 次のページ>> |
|
| 2005年3月5日(土) |
| 冬の鳥 |
|
餌求め雪の朝(あした)やカケス来る
庭の先今日も見かけし冬の鳥
餌ありや雪ほじくりし鴉かな
この三種類の鳥は性格が違っている。カケスは激しく鳴いて庭にくる、庭に餌を求めている。ツグミはいつも家の間をぴょんぴょん飛んでいる。冬の鳥というとツグミである。鴉は雪をほじくっている。それぞれ違って餌を求めているが何を食っているのかはわからない、冬の鳥にふさわしいのはやはり渡り鳥のツグミである。これは春になれば消えるからだ。
|
|
 |
| 2005年3月4日(金) |
| 春の大雪 |
|
白椿雪の重みに耐えにけり
幾度か今年は雪におおわれぬ
福寿草の庭に咲きしも
家の外春の大雪福寿草
庭に咲きしも我が籠もるかな
春の大雪だ。この時期こんなに雪がふったのもめずらしい、今年は冬が長い、福寿草もしぼんでしまう。雪はここでもめったにふらないからこんなに雪がふる景色もひさしぶりだ。

|
|
|
| 2005年3月3日(木) |
| 蕾に虫一匹 |
|
よく見れば蕾にとまる虫一つ
I happen to find out
a insect on the bud of flower
虫一匹が白椿の蕾にとまっていた。まだしかし花がひらくまでは結構今年は長い、ただ虫が来たということは春を知らせるものである。今日は昨日よりあたたかくなった。今年の寒さはここ十年経験していない寒さだった。
|
|
|
| 2005年3月1日(火) |
| 日永の館 |
|
窓広く春の日さしぬ広間かな
誰か待つ館の主日永かな
これはちょっと作った感じだが、家は広いのがいい、ゆったりとするからだ。日本の家はせますぎるし暗いのである。家がたてこんでいるからそうなる。まあ、この家は大きいだけは大きいし十分な広さがあることは確かだ。ただ見晴らしは良くないし環境はよくない、今日は福寿草も開いたし春は確実にきているが北風がまだうなり吹いている。
|
|
|
| 2005年2月27日(日) |
| 新しい店 |
|
新しき店に日永や市に来る
I stay at new shops
in the nearest city
a long day in spring
雪に散る山茶花紅し最後かな
隣の原町市には最近開店したス-パ-にいいパンがある。こうしたものは毎日のように買うから困る。遠いと買い物に困るものがある。車がないからどうしても近くでないとだめなのだ。その点六号線をまっすぐ行って近いからいい、市街の方遠くなってしまうのだ。だから市街は今はほとんど行ってない、店は六号線沿いにあった方が便利なのだ。
雪に散った山茶花の紅さ、それは最後の日、一段と紅さが映えて散る
人は死ぬ時汚いところでは死にたくない、美しい場所で死にたいと思うのが人情である。その点最後の時どうしても自然に映えることがない、汚い場所となっているからいやなのだ。いづれにしろ最後の日を意識する。常に死というのが頭を離れなかったが今や死はかなりまじかなのだ。それが若い時の死を思うのとは違う、若い時死は頭の中でしか想像の中でしかないが死は常に目の前にあるのだ。
|
|
|
| 2005年2月27日(日) |
| 雪に山茶花 |
|
雪に散る山茶花紅し最後かな
雪に散った山茶花の紅さ、それは最後の日、一段と紅さが映えて散る
人は死ぬ時汚いところでは死にたくない、美しい場所で死にたいと思うのが人情である。その点最後の時どうしても自然に映えることがない、汚い場所となっているからいやなのだ。いづれにしろ最後の日を意識する。常に死というのが頭を離れなかったが今や死はかなりまじかなのだ。それが若い時の死を思うのとは違う、若い時死は頭の中でしか想像の中でしかないが死は常に目の前にあるのだ。
|
|
|
| 2005年2月25日(金) |
| 春のアイデア商品 |
|
春を呼ぶ花二つ置き和むかな
この小さな人形はアイデアだった。こうした商品を開発すれは売れる、花だけだといつも同じであきるのだ。これに付加価値をつける。今の時代はだから物だけ売ろうとしても売れないのだ。付加価値とは壁だったら装飾とか単なる用途だけではない、機能だけではない、何か美的センスとかの付加価値を付け加えないと物あまりの時代は売れないのだ。その点これは美的センスを活かしたものとして売れる。インタ-ネットの中には実際かなり商品化できるものがある。そういうアイデアとか表現に満ちている。本にするのだって今やインタ-ネットから探せばヒットするものがあるのだ。
|
|
|
| 2005年2月24日(木) |
| 冬の鳥 |
|
今日も見ゆ人家の間に冬の鳥
今年は寒い、明日はここも雪だ。自然がいいといっても山で暮らすのは今の時代いいものではない、退職して山で暮らすことを考えている人がいるし現にそうしている人もいるがやはり町がいい、騒音などがなければ町がいい、小さな町でもいい、今山で暮らすのは大変である。冬の鳥もツグミも人家の間を飛び回り冬を越すのだ。そこにはかえって人家のあたたかさというのを感じる、庭などにも餌があるのかもしれない、山にいる鳥もいるがツグミは人家の間をいつも飛んでいる冬の鳥である。これがあまり大きな都会になると空き地などないし自然がないから冬の鳥にしてもすごしにくくなる。五六万くらいの街が人間にとって住みやすいとなる。一万くらいになると買い物でかなりたりないものがでてくる。中国人が夫をナタできりつけた津島辺りで浪江 買い物と来たから買い物自体あそこは浪江まで来るとしたら一仕事である。原町の方にトンネルできたから近いかもしれん、買い物が今はかなり必要でありその点困ることはわかる。
|
|
|
| 2005年2月22日(火) |
| 冬から春へ |
|
凧落ちてまた揚がりたし風強く
寒梅のこの道親し家まばら
真新し積む木に雪や車去る
家々に電車のひびき春の月
老女二人むつみ見守る日永かな
一瞬材木を積んだトラックが六号線を去った。その真新しい材木に雪があった。ここまで消えないできたのか、どこからきたのか、今年は寒いからまだまだ冬である。常磐線の電車は一時間おきにでている。ここは過疎地ではない、だから春の月となる。春の月の感じは場所によってちがってくる。それぞれの春があるが街がないということも淋しい、電車の音とかは全然気にならない、むしろ電車の音は何か気持ちいい生活にリズムをかなでるものである。電車の音がきこえないところは何か一段と淋しくなる。ただ車の騒音はこれはどこにいてもいやである。これが今では山の中でもそうだからいやなのだ。明らかに人間の生活にも自然にも車は調和していないのだ。それにしても岩手県の江刺が鉄道を嫌って線路を通さなかったというのも驚きである。新幹線が通り今度は名前だけも入れてくれということで水沢江刺となった。こんなに汽車が嫌われたのはなぜか今ではわからない。
凧がまだ木にひっかかてあった。誰もとろうとしない、放置されたままだ。風が強く吹いている。ここは相馬の空っ風で三月まで風が強いのだ。

|
|
|
| 2005年2月21日(月) |
| 蕪村の句をまねて(畑打つ) |
|
山路来て畑打つ婦(おんな)またありや
若竹や橋本の遊女ありやなし
蕪村の句に遊女と鵜飼とかを俳句にしているがそれがまだいるのかとかの句が多い。
生活の中である時見慣れたものが消えてゆく、それもあまりにもひっそりと消えてゆく、そこに哀感を覚えたのである。普通の人はそんなふうにして人知れず消えてしまっているのだ。大げさに騒がれるのはかえって嫌である。マスコミがそうである。芸能人なんか死んだとか政治家死んだとか大騒ぎする、しかし普通の人はひっそりと死んでゆくのだ。消えてしまうのである。
橋本の遊女といっていることは橋本という場とそこに長くいる遊女を思い浮かべている。これも今とはかなり違う、橋本という場の特定がありそこにいる遊女というのを親しく思っていた。そこには人間的な情が通うものがあったのだ。
新宿の・・・とか・・・・とか今はそこは歓楽街でもちけ中国人がいたりなんか殺伐としている。情緒がないのだ。それは甘いともなるが今の歓楽街には人間的なものがない、それが外国人だったら余計そうである。肉体だけがむきだしになっている、売り物になっている。それは外国でも同じである。何か人間的なものの喪失が現代にはある。
ともかち橋本という場には何か人間の一つの悲哀がこまった場所として深い想いがあったのだ。そうしたものは今はみんなビルの谷間と車の騒音の中に埋もれ消えてしまったのである。
|
|
|
| 2005年2月20日(日) |
| sweet spring moon |
|
春の月隣の市に近きかな
the reaching city at a short distance
and sweet sopring moon
隣の原町市まで自転車で行ってきた。相馬市となると買い物でも遠くなるからなかなか行けない、原町市は近いから自転車でも軽く行ける。鹿島町だけでは買い物はたりない、やはり本当は買い物は五万から10万くらいの都市でないと本当にいい買い物はできない、何かたりなくなる。通信販売もあるがこれもなかなかうまく利用できない、本でも中味がよくわからないのだ。今日はブックオフで10年前で5千円もした福島県の郷土史を300円で買った,これだと高い郷土史関係の本がそろえられる。本の中にまだこうしたものはあるのだ。インタ-ネットにはほとんどでていない、特に福島県関係でそうしたものをほとんど見つけられない、本の中にはかなりの蓄積がある。ただこうしたものは高いからそろえられないのだ。
英語にするとどうしてもsweetというのが春の月には必要である。単にspring moonではその感じがでていないのだ。英語にするとこうした言葉の説明が必要になってくる。直訳するだけではこの意味が伝わらないのと英語的でない日本語的表現になるからだめなのである。英語的表現に訳す必要があるのだが英語力不足でだめなのである。
|
|
|
| 2005年2月19日(土) |
| 寒梅 |
|
一部落寒紅梅の家一軒
今年は寒かった。その寒さの中に紅梅が咲きはじめた。そして寒紅梅という季語があるのをインタ-ネットで知った。それで一句できた。季語から俳句ができる。季語は漢詩の決まりのように知らないと俳句はできない、基礎的単語と同じである。こんなのまで季語にしている日本人の季節の感覚には驚くし発見だった。
寒梅の団塊の世代老いに入る
寒梅という季語も知らなかった。なぜ寒梅というのを身近に感じたかというと今年は寒かったからだ。その寒いなかに確かに数輪梅が咲いていたのだ。こんなに寒くても梅が咲いているという驚きだった。そしてこれが寒梅かと思った。寒梅というのは今まで暖冬だったから気づかなかったのだ。寒いということはやはり季節感をもたらす、これは南のような暑い所ではなりたたないような気がする。寒い北の国が寒梅がふさわしいのだ。
寒梅の数輪愛しむ隠居宅
隠居宅が何軒かありこれからもふえてくる。これもふえすぎるとまずい、医者は老人のたまり場になっているとか批判がある。いづれにしろ団塊の世代も老いの時代に入ってゆく
という感懐がある。寒梅というと老いにもふさわしい季語である。老いというのも一つの人生のテ-マであり趣き深いものがあるのだ。青年は詩にはふさわしいかもしれんが確かに俳句にはふさわしくないのかもしれない、俳句には枯れたものがあっているのか、何か老人向きなところがあるのかもしれない、ともかく今年は寒いということが冬らしくして寒さのもつ本来の冬を取り戻したのだ。暖冬というのはやはり人間の精神までたるませたし文明は季節感さえ奪うのである。
|
|
 |
| 2005年2月18日(金) |
| 春の月二題 |
|
町の空鴉帰るや春の月
spring moon in the sky on th town
crows come back to their nest in peace
昨日は雪で今も雪が残っている。ここは今頃雪が降るのだ。今日は晴れた。鴉とか雀は人に親しい鳥である。山にいる鳥とは違う、都会にもいる。都会では邪魔者になっている。町の空というとき町の家々の上を鴉がねぐらに帰ってゆく、そういう光景もあっている。そこに春の月がでている。平和な小さな町の光景である。なんでもない光景に意味があり味わいがある。それがなかなか発見されない、かえって変わった処に風趣を求める、当たり前のことに実は詩があり自然の美を発見することが芸術なのである。
玄関や昨日も今日も春の月
玄関というのは前の家にはなかった。店だからなかったのだ。今は玄関ではないが入り口がある。その前にぶらりと出てみると月がでている。春の月である。昨日は雪だったがその前は晴れて春の月だった。これからは春めいてくる。今日の三句は俳句的であった。俳句の良さはこうしてなんでもない日常を詩化できることである。やはりこれは極めて日本的な芸術なのだ。
|
|
|
| 2005年2月17日(木) |
| 納豆と長生き |
|
長生きや欠かさぬ納豆冬の暮
90になる母が毎日納豆を食わない日はない、今の世代の人がこんなに長生きなのはなぜなのか?おそらく卵を食えないほどの粗食を経験してきた人が多く、忍耐強い人が多い、そうした生活を強いられたから今食生活などに恵まれて長生きしているのではないか、一方戦後の世代、団塊の世代も戦後十年くらいは、子供の頃はかなりの貧乏だった、それなりに待望生活を強いられた、ただそれはほんのわずかな時期でありその後は贅沢になった。そのあとの世代は耐乏生活は強いられていない、余りにも贅沢になれたバブル世代となった。だからどうしても今の世代の人のように長生きするのか疑問なのだ。今長生きしている世代は耐性のある人々であり体も精神もそれ故に違っている。その後は耐性が弱い世代になっているからこんなに長生きするかは疑問である。ともかく納豆にはかなりの栄養があるし長寿食なのかもしれない、日本の食生活には長生きする要素がかなりあったのだ。しかし戦後の肉中心の食生活には長生きする要素がない、それですでに沖縄では寿命が短くなっていることがその証拠である。肉中心の生活の人は長生きするとは思えないのだ。まあ、団塊の世代は数が多いから早く死んだ方がいいとなりそれが現代の摂理にかなっているのか、今の人は長生きするべきして長生きしている。そういう時代的条件に恵まれて長生きしているのでありこのあとも長生きするのかどうかわからないのだ。
|
|
|
| 2005年2月15日(火) |
| 白鳥に鴉と鴨 |
|
鴉鴨百羽に白鳥十羽かな
月冴えて我が一人見ゆ眠る町
トラックに能代や遠き冬の暮
何故か今日鴉が百羽くらいいた、鴨も川にいた。白鳥は十羽くらいである。白鳥は貴公子であり十羽くらいいるのがいい、自然も白鳥のような貴公子とか貴族がいて鴉や鴨とか雀とか庶民がいる。どちらも必要なものである。庶民がいなければ白鳥もいないし美人でないものがいなければ美人もいないし映えないのである。
今日は多少春いたけどまだ春とはいいにくい、冬のつづきである。月冴えるというのは冬の季語だった。この季語は多いからわかりにくい、一人見る一人・・・これだけで俳句になる。自然は大勢で接するものではなく一人で接するのに向いているのだ。大勢で自然の中に入るのは労働ならいいが自然を鑑賞するのにはよくないのだ。
六号線でな能代と書かれたトラックが北に向かって去って行った。能代から来たとしたらずいぶん遠いと思った。能代も白神市になるとかもめていた。能代は前から知っているからわかったのだ。地名が変わると今までの記憶が消されるから困るのだ。能代はかなりの雪の中だろう。それにしても一体何を運んできたのかこれが今の時代これだけ車が通りすぎるのにわからないということはここを通るものに無関心にしてしまう、無関心ということはその労働に対しても無関心になってしまい心をそそがないから問題なのだ。これが江戸時代だったら歩いていたのだから必ず一人一人を見ていたし何物かもわかったし何を運んでいるのかもわかったし通るだけですでにいろいろなことがわかっていた。通る人がまたその土地と全く無関係で無関心で通りすぎることもなかったのである。常にこうしたところから文明は人間的なものを剥奪してしまったのだ。
|
|
|
| 2005年2月14日(月) |
| 白椿の芽 |
|
北風に雪ふり氷雨や白椿咲くいまだしもその芽見守る
北風うなり
庭の石は黙しぬ
白椿の芽の
ほのかに赤らめど
昨日は北風
今日は雪や
前は氷雨にぬれ
花の開くは
なお遠しかも
我はその芽に
やさしくふれて
静かに見守る
ただその花咲く日を
庭に石二つ黙しつ
家族にて待ちぬ
忍耐なくして
花も開かじ
実もみのらじ
急ぐべからじ
ただ静かに見守る
忍耐の時を持つべし
花咲く日は未だ遠しも
昨日は雪がふって白椿の芽をおおった。北風は毎日のように吹いた。氷雨もその蕾をぬらした。今年は特に寒い、しかし芸術であれ仕事であれ家族であれ何かこうして花の咲く日を望み待って生活して仕事している。子供を持てば子供の成長といつか花開く日を待ちつ生活している。そこには常にその下に忍耐が必要なのだ。何かが花開くには必ず忍耐が必要である。早急に花開かせることはできないし一人でも花を咲かせることはできない、その人が才能があってもできない、芸術でもそうなのだ。家族とかまわりのものとか時代とか技術の成長とかいろいろなものが協力して結実してくる。芸術でもこれも決していくら個人に才能があってもだめである。そうした環境が才能が活用させる環境がなければだめなのである。それを示しているのが自分だった。インタ-ネットという環境が与えられ自分が多少なりとも活かされたのである。これが本などの世界のままだったら全く活かされず終わったのである。その点すでに若い人でもそうした才能を活用させる場が与えられていることは凄いめぐまれたことでもあるのだ。それを簡単に与えられている人はわからないのである。つまり当たり前になってしまうからである。それはすべてに通じている。いろいろなものが与えられても苦労して手に入れたものでなければその有りがたみもわからないのである。
|
|
|
| 2005年2月13日(日) |
| 変わらぬ石三つ |
|
位置変えず石三つほど冬の暮
about three stones with no change
in a garden in the end of winter
人間あまりあまりに変わるのもいやになる。日本は明治維新からめまぐるしく変わりすぎた。人間関係も変わりすぎるといやになるし疲れる。年取るとやはり変わらないものがよくなる。江戸時代300年間は変化はともしかったが落ち着いた時代でありその中で日本独自のものが醸成されたのだ。これから300年間くらいは江戸時代のように変わるべきではない、パソコンも最近安定してきたから変える必要なくなったから助かる、それにしてもミラ-サイトのインホ-シ-クで契約更新のペ-ジにログインできないのはインタ-ネットの弱点だった。こういうところも安定してほしい、スム-ズにできないと安定しないとインタ-ネットで何かやることがいやになる。
|
|
|
| 2005年2月12日(土) |
| 寒戻る |
|
寒戻るさらに黙せる石二つ
the coldness come back in my garden
the two fixed stones in stillness
fixというのはどうなのか、二つの石がぴったりと庭にマッチして存在している。例えば京都の庭でもそうである。石がぴったり庭にマッチしている、石があまり多くてもだめであり少なくて過不足なく無駄なく存在する、その感じがfixになるのだろうか、ともかく今年は寒い、風が冷たい、この寒さが戻りまた石が二つさらに沈黙して存在する。
|
|
|
| 2005年2月11日(金) |
| 小千谷市の蔵 |
|
雪埋もれ小千谷市の蔵に宝かな
小千谷市の蔵が今回の地震で壊れて蔵の宝が売られて貴重な文化財が喪失することがNHKのクロ-ズアップ現代でやったがあの話は面白かった。あの辺が小千谷市縮みで裕福になり蔵をもち書画骨董類が買われ蔵に残っていたのである。
|
|
|
| 2005年2月9日(水) |
| 日脚伸ぶ |
|
前畑の土堀り返し日脚伸ぶ
前の畑がトラクタ-で耕され黒々とした土の畝を作っていた。トラクタ-だから今は情緒はない、でも前畑であり黒々とした土が掘り返され日脚伸びた、今頃は日永ではなく日脚伸ぶであった。前畑、前田、門田は農家にとって大事なものであった。今日はあたたかく春めいた日だった。
|
|
|
| 2005年2月8日(火) |
| 奴凧 |
|
奴凧枝にひっかかりにらむかな
凧は正月の季語だと思ったら春の季語だった。今は正月にしか凧はあげていない、昔は江戸時代ころは盛んに凧をあげるするのが遊びだったのだ。大人まで凧上げしていたから凧というのは世界的にも遊びとしてあった。正月だけに凧上げるものではなかったのだ。だから凧の季語が春となっているのは今ではそぐわなくなった。こういうことはよくある。今の時代には通用しない季語はかなりでてきた。ここでも凧を上げた子供がいた。でも一つくらいだったろう、それが枝にひっかかりにらんでいる。
持統天皇のとき、天下の百姓(人民)には黄色の衣を、奴(やっこ)には「くりそめの衣(きぬ)」を着用することが詔として出されます。さらに『養老令』衣服令では家人(やかひと)・奴婢(ぬひ)に、クヌギやナラ・カシなどの実で黒く染めた「橡(つるばみ)の衣」の着用が義務づけられま
す。
奴は身分の特に低いものの蔑称だった。旗本奴とか町奴とか言われたのは荒くれ男だった。おっかない顔しているからそういう人達を凧にしたのかもしれない、凧はやはり競いあい上げるところにいいところがあったのだ。それがないから死んでしまったのである。にらんでいた奴はでも昔を語っていた。
|
|
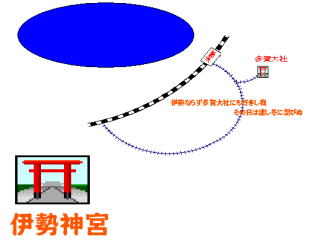 |
| 2005年2月7日(月) |
| 多賀大社 |
|
海の藍濃くして宮津古りぬるや汽車のしばしとまり過ぎゆく
旅が終わってもまた旅がつづいている。汽車が電車になったけど汽車というと国鉄全盛時代の長く走っている汽車なのである。電車というと通勤電車とか短い距離を走る感じになる。汽車という言葉には日本全国が線路で結ばれ汽車が走っているという重みがあった。長い旅をしているとき汽車なのであり通勤に利用するときは電車なのである。長距離に利用するのは今や新幹線とかになった。長い旅をするときは青春18切符などで特別にな手しまったのだ。言葉もやはりそこに長い歴史の重みを伝えるものだった。
伊勢ならず多賀大社にも行きし我その日は遠し冬に偲びぬ
これも今になると不思議だ。何十年前もの昔になってしまったから余計不思議になった。私ほど旅した人はいない、普通伊勢神宮には行くが多賀大社まで行く人は遠くからでは少ないのだ。多賀大社は忘れられた神社になったのだ。伊勢神宮は今でも天皇の社として生きているし総理大臣も詣でるから生きた神社である。しかし多賀大社は忘れられた神社になったのである。
|
|
|
| 2005年2月5日(土) |
| 冬籠もり-将棋 |
|
いつもいる将棋の相手や冬籠
24の将棋はいつもいる。これがやめられないのは点数性とか棋譜を記録して相手の手がわかるとか何かそうしたインタ-ネット独自のシステム化したゲ-ムだからだ。ともかくいつも相手がいるから便利である。どうしても気分転換とか遊びが人間には必要なのだ。外は風が吹き相当寒くてでることもできない、相馬の空っ風がこれから吹く,ここは雪は降らないが風が吹くのだ。インタ-ネットで将棋のようシステム化したコミニケ-ションを作れば人がくる。それは将棋だけではない、俳句なんかでも実際はインタ-ネット的なことをソフトを作ればできるのだ。会員制にしていれば随時様々な人の作品を分類したり点をつけたり俳句ワ-ルドができるのである。そういうものを工夫したときインタ-ネットい面白さがわかる。情報自体もそうしたインタ-ネット通信の中で組み立ててゆくと生きてくるのだ。それが今までのような本とかテレビとかのメデアの手法にこだわると生きてこないのである。旅の案内で経験者をアドバイザ-にしたのはインタ-ネット的工夫だった。あういうことをやらないとインタ-ネットは生きてこないのである。
|
|
|
| 2005年2月4日(金) |
|
|
春の月ナポリに我も来るかな
春菊や島の小さき城一つ
ナポリを見て死ねとか言っているけどあそこがそんなにいいところでもない、どこにそんないいところなのかわからなかった。イタリアは南国でありドイツとか寒い国ではアルプスの向こうでは憧れの国となっていたのだ。それでナポリを見て死ねとなったがこれは寒い国のドイツとかイギリスとかで言われたのでありイタリアの国の人が言ったのではない、ヨ-ロッパは一つの文化圏でありイタリアは日本では沖縄のような感覚になるのだ。ヨ-ロッパをみる時一つの文化圏として見る必要があるのだ。まず全体的に見て細部を見るのである。ただこれはもはや自分にはできない、一部しか見ることしかできないし理解できないのだ。ともかく私も一度はナポリに行ったのである。春菊は春の菊となっているから春に咲く花であろう。これはナポリの小さな島の城の中に咲いていたのだ。春菊というと野菜としてしか知らなかったが花として咲く、だから春菊と名付けたのだ。
思い出して作る俳句はあまり良くない、俳句は写生だからそのとき見たものを俳句とするのが一番いいのだ。あとからだと印象がうすれるし別なものを作ってしまうからだめなのだ。昨日出した冬天の句も作ってしまったから良くなかった。そのとき冬天という感覚があったのか、冬天は冬晴れのことなのかよくわからない、冬天とすると実際は大陸的な空なのだ。大陸の空は大地とともに広い、日本にはそうした広い大地だけでなく空もないのだ。空は山に区切られたような空になっている。大陸だと無際限の空とか天を意識する、日本の空の感覚は希薄である。天という感覚さえなかったのだ。これは中国から入ってきたものであり日本では単に空だったのだ。中国から入ってきたのは中国というとてつもない広い世界でつちかった文化でありこれを日本語にしたとき訳せないものがあったのは当然である。天というのは大陸でのみ意識されるものだった。いづれにしろ外国が簡単に行ける時代、文化も国際的になってくる。ただこれを俳句にするとなるとかなり困難である。詩は思い出して書いたものの方がいいのである。俳句はその時々の写生だからむずかしいのだ。
キク科の一年草。春に花を咲かせ、葉の形が菊の葉の形に似ていることから、春菊と呼ばれています。1500年ごろに、中国経由で日本に渡来し、原産地は地中海沿岸地。ヨーロッパでは、鑑賞用として栽培されており、食用としているのは、東アジア地域のみ(日本と中国)といわれています。 関西では菊菜とも言われている。
|
|
|
| 2005年2月3日(木) |
| 寒鳥三羽 |
|
寒鳥の三羽鋭く鳴き来る
Three birds twitter keenly
and flies to my yard.
翻訳機械ではこうなった。英語も日本語と同じように詩的な表現はまた違う、しかし英語とるなとむずかしい。これを読んで外国人は詩を感じないだろう。漢語が意外と大事なのである。漢語は句をひきしめるし的確に表現しているのだ。寒鳥という季語がすでに多くを語っているし漢詩には詩語として練られた歴史が長いから日本でも応用できたのである。
冬天に鋼(はがね)の強さ乙女像
十和田湖で思い出して作った句だがこれも冬天という漢語がって表現力がある。そしてブロンズなんだけれどハガネと日本語にすると何かまた別な感じなにる。やはり詩は言葉の芸術であり言葉に影響されるのである。英語では漢語のように表現できないのだ。つまりwinter sky としても何か冬天とは違う、ありふれた冬の空になってしまう。
iron strength とかなると名詞的表現でひきしまることは確かである。詩は翻訳不可能だというのは言葉のもっている感じが違ってくるからだ。その点漢語と日本語は長い間にハイブリッド化したから俳句ともマッチするのである。やはり漢字文化圏の中で日本語と合体してハイブリッド化して俳句も作られたのである。漢詩の素養のある人は俳句の表現も豊かになることは確かである。その点漱石は漢詩も俳句もできたから凄い、しかし短歌を書いていなかったのは不思議である。俳句と短歌もかなりにかよったものだからだ。漢詩はこれも相当に言葉を練って作っていないと作れない、漢詩的表現、俳句的表現、短歌的表現はみな違うことは確かである。
|
|
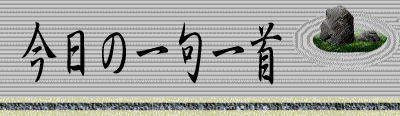
大坂-交野-近江(志賀の都)の歴史の解読2005-3-4(4ペ-ジ)
蕪村の句の不思議(邯鄲の市に鰒(ふく)見る朝の雪の解読)
桜前線の俳句短歌(3ペ-ジ)(みちのくの桜と明石の桜)新しく一ペ-ジ加え直す(