新年特集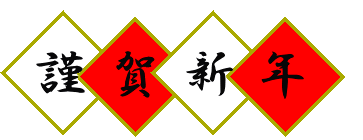 小林勇一作
小林勇一作
おちこち(紀行文集)(明治) 大和田建樹を読んで
大原女の五人三人うちつれでてくるにあう、頂きに黒木のせたるも。クルマにのせてひくものもあり。紺の着物に紺の前垂れ、八つ口帯び上げ前垂れの紐などに。赤き色のがちらがちら見ゆるも美しく。白地の手拭いかぶりつれつれ語りゆく様。よそに見られぬ名物なり。
紫車ひきいでくる乙女まで春着よそへり比叡の山もと
寂光院
山寺の汀のさくら春くれて蕨折りけむ人は帰らず
(会津へ)
秋の雨名残みなぎる里川に顔あらふ乙女八つか七つか
猿ならで落とす子供が里遠き山柿あかく色づきにけり
馬ひきて帰る童の影ばかり黒きもさびし宵暗の道
明治時代とは江戸時代が生活にも景色にも生きていた。明治時代は江戸時代と文明開化の時代の両方が存在していた。水道がないから川で顔洗う子供がいた。その川は家の近くを流れきれいだった。里川と言ったのは地元の人は里川とはいっていない、どこどこの川と言っていた。里川とか里山とは外部の人が都会の人が学者や文人が言ったのである。
江戸八おじさんのはなし
おれたちが子供のころは、里山なんて呼んじゃいなかったけど、おもしろかったなぁ。俺が12歳のころに戦争疎開して群馬のおばさんちへ行ってたころは、毎日が野山で遊ぶことくらいしかやるこたぁなかったんだ
「里山」という呼び名は、昔からあった言葉ではなく、京都大学名誉教授で
ある四手井綱英さんによる造語です。60年代頃から使われ始め、93年制定の環境基本法を受けて定められた環境基本計画(94年)に保全すべき里地の自然として「里山」が明記されて以来、一般化した。
里山は戦前までもなかった。もちろん明治時代にも里山とは言っていない、この短歌の作者も里山とは言っていないが里川と言ったのは文人だからでありこれも外から見て風流的に言った。明治時代でも都会から来ればこうした田舎の風景は外からながめるものだからそれで里という言葉を使った。山柿というのもそうかもしれん、山になっていたから山柿とした。柿は私の子供のころでも戦前でも子供のオヤツとして盗んでとったりしていたのだ。果物なども満足に食えない時代だったのである。山に住んだら里も遠いのである。車もなにもないし生活はとざされてしまうのである。だからこそそういうなかに山柿は貴重なものとなる。つまり時代をさかのぼると物が少ないから貧しいからあらゆるものの価値が違うのだ。その時代の価値はその時代のなかにあり今では計りえようがない価値があったのだ。今山柿など誰も見向きもしないからである。
朝菜つむ子も帰るさや忘るらむ冬あたたかき里川のみず
富めりとも翁の身には知らざらん木の間のけむり絶えずのぼりて
炭焼きというのはどこの山で盛んであった。信州の山の中を旅したら次から次と炭俵背負った女性とあったとか炭は生活の中心にあった。子供のころ炭を使っていたから信じられない、炭で栗なんか焼いていたのである。その囲炉裏で親父というのはどかっと座っていて存在感あるものだった。これは古い農家だと長男次男と座る場所まで決まっていた。家というのが生産の場であり大家族となるからそうした秩序が必要であった。そういう大家族というものもなくなった。だからどこでも農家は今は何か存在感がないのだ。昔は貧乏で大変だというのは本当である。ただ農家でも人でもそこ人間としての存在感があったのだ。だからこそ外から来た都会人が炭焼きなどで都会のことなど知らず自給自足している生活が頼もしいものに見えたのだ。炭焼きの煙はその時絶えるとは思いもよらなかったろう。
ますらをが安達ヶ原の真弓春くれてきえせぬ谷の卯の花
池水に水かがみするたおやめの面影老いて春暮れんとす
この真弓という地名は新地にもあった。檀であり弓の材料とか紙の材料になった。池水を水かがみするという表現はなかなか今ではできないがそういう風習が江戸時代まであったのだ。池の水で女性の人が姿を見たり化粧したりしていた。街道筋にはそうした鏡池が必ずある。この歌もやはり優れている。タオヤメという表現がまだ生きていたのだ。今の女性にそんなものを感じない、手弱女(たおやめ)は江戸時代やその前の時代の古い言葉である。言葉の意味がわかっても時代的に死んでゆく言葉はかなりある。言葉が死ぬのではなく生活に生きていないものは死んでゆくのだ。そうした古語はただ歴史として残ってゆくだけである。
晩秋の街道はや暮れ鏡池姫の姿の面影もなし(自作)
次に会津をおとずれたときの歌である。
草のみ生ひてわはれ深し。
身の丈に余りて咲ける花あざみいづれ昔の二の丸のあと
天守は今はなけれどその台に上りて見れば地下穴蔵のように深く堀りたれは埋もれもせで残りけり。
なぜここに花あざみとでてきたのか、あざみはあまり美しくはない、それが廃墟とか化した城跡にふさわしかったのかもしれない、ただスコットランドの花があざみなのである。
その昔、スコットランドは北海の海賊・ノルウエ−と長年に渡り戦い続けていました。時は1263年、スコットランド西部のラグ−スにノルウエ−軍が上陸、夜襲をかけて来ました。その時、素足のノルウエ−軍があざみのトゲを踏み、大声を出してしまい、それによって夜襲を察知したスコットランド軍はノルウエ−軍を撃退、勝利しました。
この時から”あざみ”はスコットランド救世のシンボルとなりました。
あざみはスコットランドのような北の荒野にも咲く花だから国の花になったのか、普通あざみに注意する人は少ない、花というより草に思えるからだ。
杉むらの 秋の日うとき 下草に 心つよくも 咲く薊かな(正岡子規)
井戸は城内に七つあり。されどいづれも水あらずして、瘡のみ縦横に枝葉さしかわしてのぞぎ見たるは身もふるはるるほどなり。官軍と戦いし以来水かれたりと。車夫の語るは誠なりやいかに。一二ありたりといふ矢倉のあたりなど。まわるまわる堀りを望めば石垣高く水青く、すごきことたとふべからず。あれなる小田山より官軍に砲撃されたるが。ごらんぜよ、この大杉の幹に打ち込まれたる玉は今もぬけずして留まれりと
玉を身に受けて引かぬ大丈夫のこころかくこそあらまほしけれ
この花の世に咲きいでしほどなくも散りて香りを残しつるかな
明治時代会津を訪れたらその感じかたは全然違う、あまりにも生々しくリアルに感じる。実際今の城は新しく建てられたものであり無惨な城の姿があった。荒廃した会津があったのだ。青森の斗南では飢えて乞食までしたとか悲惨であった。武士の操がここに最後まで残った。そのなかでアザミのように咲いてたくましく生きたものもいた。そこには語りつくせぬ物語がある。
(松平家の墓所)
槍たてて詣でし人の古をおもへばさびし蔦の細道
(三人の女人の墓のならびたる会津滅びて夏草繁し-自作)
槍たててなど表現するのもそのとき侍の姿が眼前に生々しく浮かんだ時代なのだ。明治は江戸時代の景色や人物も侍など現実のものとしてなおリアルに生きていた。二つの時代を生きていたから今ふりかえると魅力ある時代になっているのだ。江戸時代の人間は文明開化した明治の人間と違っていた。これは間違いない、今当たり前と思っている人間と江戸時代の人間は違っていた。それをどう表現していいかわからないが違っていた。やたらに泣いていたというのも情が厚いからである。この作者も人と会いまた別れて泣いている。まだ旅というのは遠く難儀なものだったからである。
電車の中
日比谷より新宿の電車中、向こう側に腰掛けて雑誌を読む男あり、三宅坂を上る際に電車がたがた音して、進行やややおそし。その男たちまち何事ぞとどなる。そのとなりに腰掛けたる人あわてておりんとするにその男の洋傘たおしたり。怒鳴って靴にてける。その男の眼と眼とあいしに、ぐっとにらみつめ、まただきもせず、。
癇癪の甚だしき相にて、まかりまちがわば狂人になりそうな目つきなり。恐ろしくなりてわれ眼を転じぬ。英雄、豪傑は必ずしも恐るるを要せず、馬鹿と気違いとが恐ろしきなり。(大町桂月)
大町桂月は侍の作家だった。明治二年生まれでも侍的なものが生々しく残っていたのだ。この光景はなんでもないのだが侍が電車に乗っているのを想像するといい。文明人にはこういう人が多い、今でもそうである。そんなもの当たり前だから注意もしない、何かいろいらした人が多いのだ。江戸時代や明治のはじめにはそういう人がいかったがそういう人がふえてきた。それで大町桂月のような侍でも不安になった。対処する方法がない、何をしてくるかわからない、侍のような礼儀も作法もない、何をしてくるかわからない恐怖を感じたのだ。まさに文明人はそういうものが普通ではないか、電車にのりあわせると今よりそれはひどい、それを狂人のように感じた、何か人間的情とか繊細さとか礼儀とか作法とか日本人的なつつましさとか江戸時代からもっていたものが喪失してきた時代の人が現れたのだ。馬鹿ときちがいが英雄となったのがなるのがナチスとかカルトの時代なのだ。そこに文明の恐怖がひそんでいるしそれが現実となったのが現代なのである。
いづれにしろ文学でも人物でも景色でも江戸時代から明治や戦前の方が日本は生きていた。確かに現代は物質には豊かでも不思議に日本という大地に根付いていない空虚さがある。大都会化、極端な工業化の中で大地に濃厚な生活がないから死んでいるのだ。逆にそれだからこそ国際化で世界と伍してゆけるということはある。でも日本の大地が死んでゆくときそこに本当の栄いがあるのだろうか?栄いとはその国の自然とともに大地とともにあるものではないか、それをどうしても感じてしまうのである。だから過去をさかのぼるとかえってそこに日本的なもの風景でも人物でもよみがえりほっとするのだ。それはただ想像の世界にしかないという悲しさである。でも掘り起こせばそうした過去はうかんでくる。そういう歴史は今になると千金の値にもなる貴重てものだったのだ。それは失われてはじめて理解したのである。常に歴史は人間はそういうものかもしれない、失ってみてはじめてその価値を知るのである。老人になりはじめて青春の価値をしり連れ添いのものを失ってはじめてその価値を知りとそういうくりかえしが人間だったのである。
御民われ生ける験(しるし)あり天地(あめつち)の栄ゆる時にあへらく(万葉-996)
天地とともに栄えてこそ生きる験(しるし)がある。生きたかいがある。それがないから何か空虚なのである。大地からの実りを自らかりとり手にするとき本当の実りがある。工業や商業の肥大化が何か社会を歪(いびつ)にしてしまっているのだ。日本の天地が生きないことには本当の栄いではない、そこが次の時代の課題なのである。
国立デジタル図書館へ
http://kindai.ndl.go.jp/cgi-bin/img/BIImgFrame.cgi?JP_NUM=41011330&VOL_NUM=00000&KOMA=4&ITYPE=0
評論と鑑賞目次へ
小林勇一作