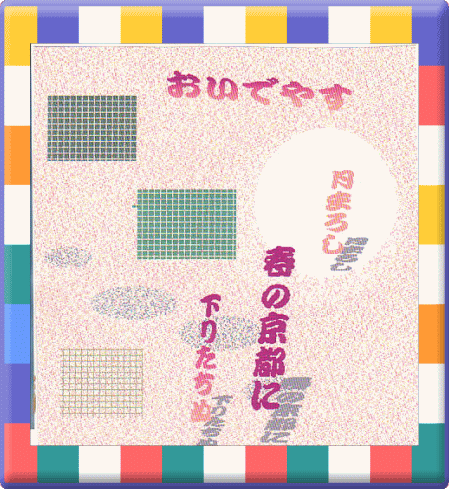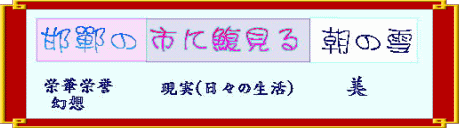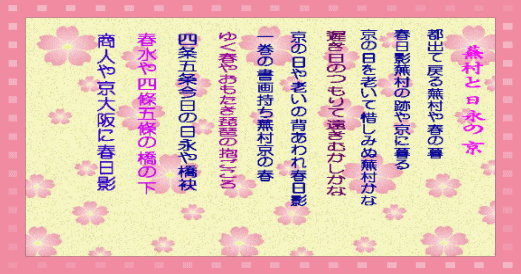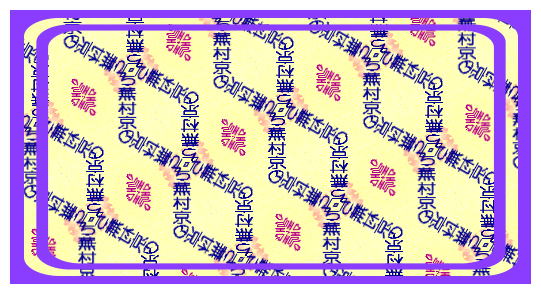蕪村の句の不思議(邯鄲の市に鰒(ふく)見る朝の雪)(小林勇一)
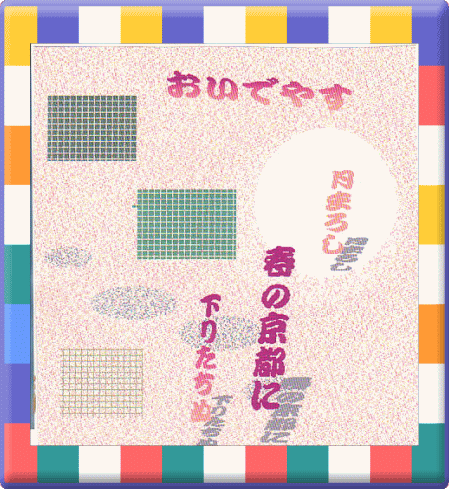
●終の住処は都
都出て戻る蕪村や春の暮
春日影蕪村の跡や京に暮る
京の日を老いて惜しみぬ蕪村かな
遲き日のつもりて遠きむかしかな
京の日や老いの背あわれ春日影
一巻の書画持ち蕪村京の春
ゆく春やおもたき琵琶の抱ごころ
四条五条今日の日永や橋袂
春水や四條五條の橋の下
商人や京大阪に春日影
みちのくゆ訪ねて遠し京の春貴人の棲める跡のゆかしも
白雪に見紛う花の散れる庭夕べに赤き落椿かな
蕪村の句は不思議なのが多い、芭蕉の句は旅をテ-マとして終わっているが蕪村の句は都から京都にその墓があるように京都という都から離れなかった。都が彼の住処であり帰る場所だった。この都というとき必ずしも現実の都だけではない、心の中にイメ-ジとしてふくらませられた象徴化された拡大化された、イメ-ジとして現実の都からさらに作られた都があるのだ。現実の都だけではたりない、その現実の上に幻想化された都が重なるとき都はさらに現実以上に華麗なものとなる。だからかえって都は離れていた方がいいともなる。簡単に行けると都の価値も落ちるのである。いつでも今や京都なんか行けるではないか、京都も他の街と今や変わりないとか都に対する有り難みがなくなってしまうのだ。余りに便利になって今や場所の価値は低下してしまった。京都ですらありふれた誰でも行ける場所になったので価値は低下してしまったのだ。だから現実の都とバ-チャルの都の新たな創造が必要なのである。バ-チャルな都の方が豊かになるということがあるのだ。
ともかく人とは最後にそうしたついの住処を持つのか、場所は旅に病んで夢は枯野をかけめぐるで死んだ。死に際にも旅していたのだ。一茶は雪に埋もれた土蔵が終のの住処だった。それぞれの人生、個性にふさわしい死にかたが終の住処がある。管江真澄というみちのくを放浪した人は角館で死んだ、これも全く謎に満ちた人生だった。これは芭蕉より旅したというより旅を常住としていたのだ。こんな生活を江戸時代にできたこと自体不思議である。人間とはこうした個性ある生きかたというのがやはり後世にいつまでも語られることになる。謎であり神秘的になるからそれが伝説化したりする。上野霄里氏という人も謎に満ちた人間である。もともと神秘性があるのが人間でそこが人間の魅力だと自ら言っているから彼自身も謎なのである。
雪埋もれ真澄の墓はみちのくに語れる昔心にしみぬ
みちのくの寒さやあわれしみじみと真澄残せし文をよむかな
ではこの謎なる人間を解く鍵はどこにあるのか、それは本人が行動したことはいろいろ尾ひれがついて何をしたのかがわからなくなる。その行動は大げさに誇張して語られたり本当の姿を伝えないことが多い。だから坂本龍馬は単なる西郷などの使い走りにすぎなかったとかなる。明確な証拠がないからわからないのだ。誇張して祭り上げられることにもなる。一方芸術に関してはともかく作品が残っていると一首でも一句でも残っているとそこからその人間を見てゆく、個性を見ることになる。それを手がかりとしてみる、それはまぎれもなく本人が残したものだからその本人を語ることになるのだ。だからその本人が書き残したものはどんなものでもその人なりを伝えることになるのだ。例えば高杉晋作という人を理解することもむずかしい、ただの暴れん坊だとか無頼漢だとかいう評価もある。でも彼が残した短歌を知っていい短歌作っているなと感心した。漢詩も作っているし詩の素養があったし三十前ではたいがい短歌とか漢詩でもいいのは作れない、啄木などは例外だし宮沢賢治なども例外である。普通の人は若いときそんなにいいものを作れないのだ。
高杉晋作は野山獄へ投獄されたとき作った歌である。
今さらになにをかいわむ遅桜故郷の風に散るそうれしき
これが非常に気に入った。これが30前で作れる不思議である。遅桜というのは普通なら40位とか遅咲きの大器とかの例えにされる。故郷に生きて老人となった遅桜なのだ。だからこそ散っても悔いないとかの意味になる。これが30前にして作れる不思議である。江戸時代の人間は早熟であることは確かである。今の人間とは感覚的にもかなり違っていた。非常に大人びていた。明治時代の人間もそうである。現代の人間は成熟するにはかなりの時間がかかる。モラトリアムの時間が長くなる。あまりにも情報化時代で肝心の情的な部分の発達が遅れる。知識過剰の頭でっかちになっているからだ。知識はあっても情的には発達せず子供になっている。そうしたアンバランスな人間になってしまっている。
●生活実感と幻想の美
冬木立北の家かげの韮を刈
普通韮というものに農家の人でなければ興味がないし出てこない言葉である。わざわざ北の家かげというのも一段と寒い冬の感じをだしている。ここに韮を出したのも意図的なもの、写生ではない、ここには韮が必要だったのだ。韮を出した事で一層寒い感じがでている。農家に暮らしたからこうした感覚がでてきているとしか考えられないのだ。蕪村にはこうした句が多いのだ。そしてそこに美的なセンスが絵画的に描写されるのである。絵画的な詩人であったことは確かである。一つ一つの句が一幅の絵になっているからだ。
蕪村の句の不思議はそうした農民的な生活感覚をもっていたことなのだ。農民でなければ作れないような句がかなりある。農民を客観的にみるのではなく自らが農民になったような生活実感として句を作っている。
例えば
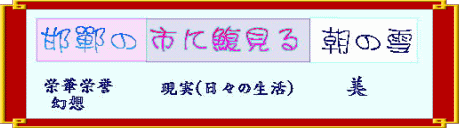
この句はもっとも不思議ではないか、蕪村を象徴している句ではないか、というのは邯鄲いうとこれは栄誉栄華の世界であったがこれは夢と消えた。まるで浦島太郎が龍宮城に行って夢見た世界である。夢から覚めたら玉手箱から煙がでてすべては消えてただ一介の白髪の老人がいるだけだったのだ。これが別に特殊な人生を送った人ではない、みんな老人になればそうなっていることに気づくリアリティのある物語なのだ。人生を集約したような話なのだ。
邯鄲は夢の世界であり一方鰒(ふく)は河豚のことであり(河豚の話)毒のある魚でありこれはまたうまい魚である。これは何を意味しているのか、毒あるものが市場で売られている、この現実の世界は実際はかなり毒のある世界である。その毒に触れて一命を落とした人間はいくらでもある。だまされたりだましたり殺人もある。この世を生きるとは毒の魚を食うことでもある。そういう世界が現実である。市場は毒ある世界である。マスコミでも出版界でもそこは実際は利益に奔走する毒ある世界である。この世自体強烈な毒ある世界であり純粋なものを追及する世界ではない、芸術家も市場に出れば毒にあたる。寄ってくるものは金儲けだけを考える人間かもしれない、金儲けの為に利用しようとかそうしたことが多いのだ。精神的価値を追及するものは市場化と相いれないのだ。そうした河豚という毒ある魚が売られそれに朝の雪という清涼な強烈な美の世界がある。一朝目覚めてみたらそうした現実があったのだがそこにも強烈な美の世界があった。浄化されるような雪の美の世界があったのだ。それがまことに不思議な世界である。なぜここに河豚をもってきたのかもこれも何か意図的なのである。別な魚でもいいのだが河豚がここにもってきた作者の意図があるのだ。
子規の「蕪村句集講義」に

の解釈に
「一句の意はふぐ汁を食う家の明るく灯をともしたる様をいいたるにて、もし河豚を食うて死ぬるものとせばあはれにもの悲しくなくてならぬにこれはまた引きかへて陽気なる景色を現したるなり」
ここに河豚をもってきたのはやはり作者の意図がありもってきたのである。そもそもこの句自体写生ではないからだ。河豚は確かに特別うまいもの、人生を魅了するものなのだ。正に誘うように赤々と灯っている、しかしそこには毒があるのだ。女性の美もそうである。それは毒が秘められた美である。それを知っていてもその美にひかれ毒にあたることがある。あえて毒にあたっても鰒(ふく)を食うのが人生である。エイズになるからよせと言っても買春とかやめない、人間の欲望の深さがそうさせているのだ。
ふぐ汁の我活キて居る寢覺哉
これもまた危ない世の中をふぐ汁を食ってきたがよく生きてきたという感慨である。蕪村は実際芭蕉と違いかなり世俗の中に入って生活したからそれを特に感じたのだ。
この短い句のなかに人生というものが凝集されているのだ。この句はだからもっとも不思議な句の部類に属する。写生というものもここにある。それは架空ではないそういう光景は現実にある。市というのは日々経済生活する場であり人間はそこで生活せねばならぬ。人間の生活には日々の経済生活が欠かせない、しかしその中にも美を織りなす世界がある。織物は単に防寒用具ではない、美しい紋様が織りだされる美の世界を作ってきたのだ。実用がありまた美の世界の追及が人間の生活なのだ。それは自然の中で生活するすべてにあてはまる。自然そのものが美の世界になっているから当然そうなってゆくのである。そうならない文明世界はやはり歪んでいる。美はすでに自然に存在しているから人間は作り出す必要はなかった。美はふんだんにあるものをとり入れるだけでよかった。それが文明が遮断してしまったのである。
邯鄲の見た夢の世界はそれは栄誉栄華の現実の世界ではなかった。権力の栄華の世界はかなく消えてゆく、しかし人は常に求めている、権力の栄誉栄華の世界をそれは庶民すら求めている、王様になるというのではなく庶民の夢は政治家になるとか億万長者になるとかスタ-になるとか邯鄲の夢は尽きることがないのだ。それがこの世である。王様になる夢は本当に夢だったが今や庶民の夢は意外と身近にあり本当に実現される夢なのである。そういう幻想をあおるからこそ宗教団体が反映しているのだ。宗教は今や昔の宗教とは全然違う、現世利益を求めているのだから邯鄲の夢を見ることなのである。
つまり人間というものはこの句に凝集されるように変わらない、必ず邯鄲の夢を見たいのだしそれが覚めてみれば市で生活する現実がある。そこに朝の雪という現実の美もある。こういうことが人生ではくりかえされてゆくし人間は輪廻するというのは本当である。人間はこれだけ技術が発達したからといってその本質は変わらないからこそこの句も生きてくるのだ。美人と暮らす夢とか華やかな衆人にもてはやされる生活を夢見ているのだ。この句は変わらぬ人間を語るが故に不朽の価値を持つのである。青年時代に世の中を見るのと老人になって世の中を見る目はまるっきり違ったものとして見える。青年時代は華やかなものものにひかれる。老人はそれは邯鄲の一睡の夢のように消えてしまうのが現実として実感としてわかるのだ。一体何してきたのだ人生とは煙を空をつかむごときものだということがわかるのだ。狐にたぶらかされたようなものでありそのはかない夢にふりまわされて一生終わる。そのことは人間であるかぎりくりかえされてきた事であり不思議な事でもなんでもない、でも青年時代は以前としてこれがわからないのである。だからいつまでたっても人間は同じ事をくりかえしているのだ。邯鄲の夢はいつまでもつづくのである。それは科学技術がどれだけ発達しようが変わらないのである。人間の欲望は変わらないしその欲望がなくならない限りこの世は同じ事の繰り返しなのだ。
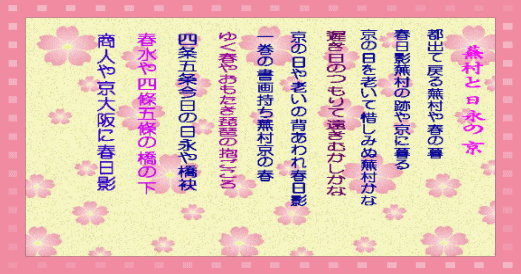
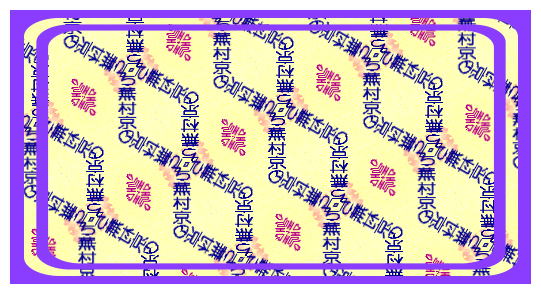

花あまた色濃く映す京の池
蕪村の句から江戸時代を偲ぶ(生活感覚の俳句)
評論鑑賞目次へ