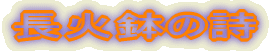江戸時代の魅力(江馬細香の漢詩から)(小林勇一)
江戸時代の魅力とは何か、今の時代に失われたものがあるということだ。例えば何回も現代の旅について書いたが旅は失われたが当時は本当に旅があった。旅は容易にできるものではないし別れには水盃をしたり大変な覚悟が必要だったのだ。それ故に旅は存在した。その道中は通りすぎるものではない、西行のいう「命なりけり」とまではいかなくてもその命懸けになる旅に対する思いは今とは全然違っていたのだ。最近気づいたのだが旅を知るには現代からは知りえようがないことがわかった。旅は現代から喪失した。今の旅は単なる移動であり保養であり旅ではない、汽車の旅にしたって結局通りすぎて行く旅であり頭に残るのは駅の名であった。ただそれから私は地名に興味を持ったのだから無駄だとはいえない、でも旅そのものが欠落していることに気づいたので自転車で旅を試みるようになったのである。
桂小五郎が萩から江戸に旅立つ時に記されている。
かへらじと思ひさだめし旅なればひとしほぬるる涙松かな
涙松があるとするとその松には旅人の思いが託されているからそうした名前がついて残っているのだ。街道に立っている松には旅人の思いが託される。当時の旅人にとってその道中に接するものに特別な思いがあったのだ。今のように気軽に旅には行けないし自動車のようにバイクのように過ぎさる旅ではないからだ。だから現代からは旅そのものがなくなったのである。
明かりにしてもそうである。全然今の感覚と違ったものとして明かりを灯を見ていた、利用していた。そしていかに当時の闇が深く暗いものなのかまた静かな夜があったかなど環境が全然違う、真夜中まで煌々と電気の光に満ちている世界とは全然違う。まさにそのことが今になると魅力なのである。そういう闇と静寂の世界を失っているからだ。
「ろうそくの値段は非常に高く、広間に使う大型の百匁ろうそくともなれば、十九世紀はじめ頃で一本200文(5千円)くらいだった。」
冬夜 江馬細香
書爺繙欧蘭書
句児読唐宋句
分此一灯光
源流各自泝
爺読不知休
児倦思栗芋
堪愧精神不及爺
爺歳八十眼無
冬夜(とうや) 冬夜
爺(ちち)は繙(ひもと)く欧蘭(おうらん)
児(こ)は読む唐宋の
此の一灯の光を分かちて
源流各々自(みづか)ら泝(さかのぼ)る
爺は読みて休(や)むことを知らず
児(こ)は倦(う)みて栗芋(りつう)を思ふ
愧(は)づるに堪(た)ふ精神爺に及ばず
爺は歳八十眼に霧なし
この詩の魅力は「此の一灯の光を分かちて」というように光が貴重であったことなのだ。その貴重な光を爺と孫が分かち合い勉強するということにほのぼのとしたものを感じるのだ。つまり物が少ないから貧乏だから助け合うということがある。かえって貧乏なときは人は助け合うのだ。インドでも乞食に施しするのは貧乏人であるという、少ないなかから与えているという、なぜかと言うと自分も貧乏だから相手に同情するからだ。一方金持ちの施しは義理みたいなものである。一つの強制的税金とにている。日本の外国への援助もそうである。金持ちの義務であって同情心ではない、当然の義務として要求されているのだ。この詩がなぜいいかというと世代間のつながりがあり家庭のなかで学ぶということ、ともしい光を分かち合い学ぶということこれらは現代になくなったことである。家庭にすら世代間のつながりがないし教育といえば学校だし家庭という場がもっていた様々な機能の喪失があるからだ。そして豊かになるということは奢りをうむ。なんでもあれば分かち合ったり助け合ったりしないのである。まさに現代は余りに豊かになった結果人はその家庭内でも助け合わず子供を虐待するまでになる。確かに豊かでなければできないことが多いし貧乏な時代を美化しすぎるとなるがでも貧乏でなければありえない人間の豊かさというのが江戸時代にあったのだ。それが江戸時代を偲ぶ意味である。
蕪村の句も当時の暗闇の中での微妙な繊細な感覚から生まれた。暗いことは人間の感受性を敏感にする。細き燈の中で浮かぶ雛は怪しいまでに美しい。かえってその美を際立たせる。
こういう環境でかえって美の感覚が磨かれたのだ。今はこうした美が騒音やら物の豊かさのなかで破壊されている。人間がもっていた本来の感覚が失われる、損なわれるのだ。原始時代の人間の方が五感をものすごく鋭かった。遠くの鳥の声もすぐに聞き分けたしその感覚は全然違っていたのだ。詩というものもこうした人間の本能的感覚がうすれればいいものはできない、芸術にしても感受する能力が減退すればいいものはできないのだ。現代は機械とか物は豊富だがその目がコンピュタ-になりその足が自動車になりその手がロボットになり人間の存在はいらないとなる時代である。これもまた奇妙である。人間の代わりがすべてロボットになって人間はいらないとなる。しかしロボットに人間の代わりはできない、ロボットは俳句一つも作れないからである。あることに関しては明らかにロボットが代わりになる。最近の翻訳などはかなり人間に近づいているし他にもあるが創造的な作業はロボットにはできないのだ。主役は人間である。
江戸時代であれ明治であれ戦前であれそこにはまだ濃密な人間中心の世界である。物は少なくても貧乏でも人間が濃厚に存在している。存在感のある時代なのだ。現代は極端な物質文化によって人間が卑小化された時代である。ビルとか自動車とか様々な電化製品やらに囲まれて人間が見えないのだ。茶の間の中心にあるのがテレビなこともそれを象徴している。マスコミに出てくる芸能人が茶の間の主人公になっていること自体、家庭という存在そのものが存在感を喪失しているのだ。江戸時代には茶の間にテレビもない、だからその存在の中心は家庭でありそこに生活する人間なのである。農家でも囲炉裏がありそこが生活の中心である。そこには濃密な人間の息づく場でありテレビが中心の世界とは違うのだ。その中で主の座がゆるがないものでありそれを軸にして家庭が成り立っていたのである。だから長火鉢があるとするとそこからは人間の匂いが存在感が今でも濃厚に感じられる。そこには確かに人間の存在があった。それが今なら一つの物があっても存在感ない、外見は装飾豊かでも何か空疎なのである。人間そのもの存在感喪失しているからだ。ビルにしてもビルというのは人間の存在感をまるで感じさせないのだ。ビルのなかに人間さえいると思えない、だからビルが空になるとそこに人間がいたことさえ感じられるなくなる。つまり事務の機械やパソコンがそこに残りかたずけられるように人間の存在が希薄なのだ。それはこの文明のあらゆる分野にいえる。人間の存在を示すものが希薄なのだ。それに耐えられない大きな人は天才などは上野霄里氏のようにアウトサイダ-として人間の存在を誇示するようになる。存在感とは何かというとそれはありふれたもののなかにもある。例えばいつも通っている道に一本の枯木があった。これはいつも見ていたのだか注目していなかった。しかしここにも一本枯木が真っ直ぐに立っている。それが頼もしいと思った。ただそれだけのことなのだがその存在感を確認した。
一本の枯木が真直ぐにここに暮る
なんだ、一本の枯木がそこに立っていた、それがどうしたのだともなるがしかしその存在を確認したということはその存在に気づいたのである。では都会のビルにそうした存在を感じるかというと感じないのだ。それが人間を圧迫するものとは感じても肯定的に存在することが確認できないのだ。だから現代は人間不在の時代である。江戸時代の魅力はまさにこの喪失した人間の日常があったことである。特別の人でなくても江戸時代の人間には生活の中で人間が存在感があったのだ。その人間に焦点があてられ今のようなあふれる物とかビルとかに人間は隠されないし卑小化されないのである。
静かな時が流れている
主は長火鉢に座り
長煙管をとりだし煙草を吸う
一服吸いまた一服
煙はゆらゆらと天井に達して
とんとんと煙草盆をたたきヤニをだす
その側にはいつも誰かがいる
女房が側によりうなづきあいづちをうつ
いつも主の語ることを聞いている
主はおもむろに語りまた黙る
静かな時が流れている
何時か知らぬ
黄八丈が襖にかけてある
島の人丹念に織りたるものそ
末永く着るべきものなり
物といえばわずかなもの
ただそこにしめる座
そこにはいつも主が座っている
その座は変わることがない
そしてその主の座の側には
いつも耳を傾ける女房がいる
一人ではない誰かがいつもいる
炭をくべる、炭は静かに燃える
寒中に物売りの声がひびく
江戸とはいえ夜は暗く静まる
丑三つ時の鐘がなる
江戸八百八町は眠りにつく
長火鉢は主なきいまも
そこに主がいて女房がいる
誰かがそこにまだいる
二人は離れようとしない
いつまでもそこにいる
そのぬくもりをまだ感じる
人がそこに影となりいる
その声も存在も感じる
主はそこで何をかを語りつづけている
その物語は終わっていない
そこにはなお主がいる
その主が語るのを聞くものがいる
物語は終わっていない
延々と物語はつづく
人の生は一代で終わることはない
たとえ消えても存在を語りつづける
それが人間の生であり歴史だ
切断されて途切れてはならぬ
生は連続し語り続けられる
一代で語られぬものが
次の代に語られ次の代に語り継がれる
それが人間の生であり歴史だ
古いものにこそ根はあり
新しいものは古い根から育ち
古い根は切られてはならぬ
古い根がありて新しいものがある
古いものは見直されて
また新しいものとして再生する
この写真はまもなく消える-無断拝借だから
評論鑑賞目次へ