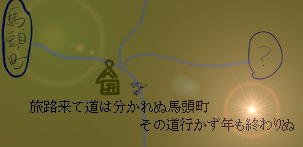失われた馬との生活(俳句エッセイ) 小林勇一作
野馬追いに飼われし馬や秋に入る
野馬追いでしか使わない馬が何カ所かで飼われている。馬と人間が暮らした年月は長いのだ。自動車と人間の歴史が始まったのはここ二三十年である。馬は実際私の子供の頃、実用としてあった。馬車屋があり荷物を運んでいた。その馬車の後ろに飛び乗って遊んでいたのだ。これも信じられない話である。だいたい戦後十年までは昔が残っていた。それがその後急速に高度成長になって消えてしまった。馬というのも消えたということこれも何か人間の生活に大きな喪失感をもたらしたことに気づいていない、馬は人間と一体であり馬と人間にまつわる話は無数にある。馬も生き物だから人間として自然と情が通うから死んだら馬頭観世音とかを建て供養したのである。
あるところに貧しき百姓あり。妻はなくて美しき娘あり。また一匹の馬を養う。娘この馬を愛したので父は馬の首を切り落とした。娘はその首に乗りたるまま天に昇り去れり。オシラサマというはこの時より成りたる神なり。』(遠野物語六九話)
馬の話
http://www.jtng.com/~syhtms61/p40/p40.htm
これも馬との濃密な関係を語っている。動物と人間は今とは違う血肉を分けるような一体化した関係にあった。だから神話になったりもするし祖先が動物になっているのも多いのだ。
この馬が全く現代から忘れられてしまった、競馬とかだけの馬としてしか見ていない、競馬はギャンブルの道具であり馬として生きる姿ではない、全く不本意な馬の使い方なのである。馬も文明によって追放されたのだ。
実入りよき岡部の早田赤らみて 史邦
里近くなる馬の足音 玄哉
これは芭蕉が死んでから久しくを経て世に現れた「年忘れの歌仙」と柳田国男全集にある。ここに早田(早稲田)とは里の実りをいち早く示すものであった。「赤らむ」とあるがこれは農民でないから実感としてわからない、早稲田はすでに刈られてしまった。早く刈られた跡を見て早稲田だったと気づいた。その稲穂を見て早稲田とわかるのは農民だけだろう。
「里近くなる馬の足音」とは馬が里を出て遠出して里に帰ってきた喜びのうよなものがある。人間でも遠くに行き家に帰る喜びがある。ここに馬というものと里の暮らしがマッチしている世界があったのだ。馬は農民の生活と密着してあったのだ。柳田国男の説明では村に近寄るほど方々から馬が集まって足形の窪みがしだいに多くなってくるので野中の道もやや里近くなったと知る、これは現代なら山道を歩いて舗装の道に出るような気持ちだろう。現代ではまずこんな気持ちになることはない、馬で行くにしても里から離れればかなり遠い感覚になるのだ。だから里に近づくことがなつかしくなる、ほっとするのである。ここまではなかなか馬のことは想像しにくい、彼は馬のことを知っていたのだ。まだ馬と暮らしていた時代でもあったからだ。この連句はこうした昔をふりかえると当時の村の生活を彷彿とさせるものがあるのだ。
馬というものはここで野馬追いなどに使うだけで全く生活から切り離された存在である。このときしかし馬は人間と共に大地と共に生きていたのだ。人間と共に生きていた失われた馬の息使いがここに聞こえてくる。早稲田とは何を意味していたのか、これも過去にさかのぼらないとわからなくなっているのだ。早稲田という地名があり早稲田大学となった。馬と人間はかつては一体でありだからそこに馬と人間の物語が残された。今は自動車と人間の物語になるのだがこれがこうしたなんともなつかしいというかそういう風景ではなく交通事故とかの殺伐としたものとして現代はあるのだ。自然というとき現代では生活から離れたものとしての自然であり登山とか観光とかで自然を鑑賞する、客観的に鑑賞する芸術家のようになっているのが自然とのかかわり方である。動物にしても生活のなかで曲家のなかで馬や牛と一緒に暮らした一体感とは違う、都会人は自然と隔離された中に暮らしているから機械やビルとかの谷間のなかで暮らしているから自ずと和みがなくなる。自らもロボット化する。ロボットなんか本当に必要なのかと思う。もっと人間的なものを人は求めているのに逆の志向になっている。なぜお釈迦様が草木にも仏性があるとか草木も成仏するとか言ったのかこれは自然との一体に暮らしていたなかで文字通り自然発生的に生まれた感情であり理屈ではないのだ。そもそも宗教は理屈ではない、人間の生きる喜びは万物と一体となりその中に自らを見いだすことである。そこには動物も植物もただ食うものとしてだけでなく生命の輪として存在する。そんな思想が法華経や賢治の思想にあった。現代文明人は自然とのつながりを失ったということは人間ならざるものロボットになっゆくということを真剣に考えねばならぬはずだが以前としてただひたすら技術の進化を追及している。それが必ずしも人間の幸福に結びついていないことに問題があるのだ。
例えば鴉にしてもそれは都会ではやっかいなものとなる。ただゴミを食いあさるやっかいなものとして排除するだけのものとなる。鴉も明らかに生き物であるがこれを排除することのみになる。
同じ道昨日の鴉や秋没日(あきいりひ)(自作)
田舎で毎日同じ田んぼの道などを行く、するとそこには昨日いた鴉がまたいるのである。そしてその鴉と里の秋没日をともにながているのだ。つまり鴉とも鳥とも自然の中に一体化してくるのだ。そこに鴉も里の自然のまぎれない一部となっている調和した姿がある。都会にはこれがないのだ。だから都会にいれはどうしても感覚的にかなり違ったものになってくるのではないか、自然の見方がまるっきり違ってくるかもしれない、つまり鴉とも一体化する自然観は育まれないのだ。何度も言っているように情が育まれないのである。
雪の暮鴨(しぎ)はもどつて居るような(蕪村)
これはどこかしらないがともかくここに何度も来て鴫を見ていて、この鴫が友のように親しくなっていたのだ。そういうふうに親密に自然の生き物と接することは普通都会ではないだろう。蕪村は都会人でもあったが今の都会人とは違い、農民的な生活感身についていることがこうした句を作らせたのかもしれない、動物も人間にとって手足のように親しいものだった。だからエジプト文明では人間と同じように牛でも大きな墓に埋葬しているのだ。インドでも牛を大事にするのはそうした感情があるからだ。それこそ人間を人間足らしめるものだったのだ。遅れた文明でもなんでもない、人間的な文明でありロボットと機械と一緒に葬られるよりは動物と一緒に葬られた方が幸せなのだ。ただその穴埋めとして現代人はペットに可愛がるのもその喪失感を穴埋めするためなのだからやはり人間は自然との一体感があって人間たりうる存在なことを如実に示している。事実、ペットの墓を扱う所がふえている。これもエジプト人と同じ感覚であり迷信的でもなんでもない、人間の本質に根ざした素朴な感情なのである。
馬の顔少女なでるや秋の風
婆さんと孫がいて孫が馬の顔なでる。ここでもすでに馬との情が交わされるから人間は情が育まれてゆく、しかし自動車洪水と機械と遊ぶだけの人間に情は育まれない、殺伐とした人間も育つのもそのためではないか、文明は確かに便利だし合理的だし豊かにはするのだが何か根本的なものを欠けさせる。非合理的なこと、能率的でないこと、無用なこと、暇なこと、急がないこと、金に追われないこと、・・・・こうしたことが人間的にする要素でありこれは教育でも変えることはできない、そういう環境にいることが大事だからだ。
折口信夫は、歌集「供養搭」を遺している。
人も 馬も 道ゆきつかれ死ににけり。
道に死ぬる馬は仏となりにけり。
いきとどまらむ旅ならなくに
山の松の木むらに、日はあたり ひそけきかもよ。旅びとの墓
ひそかなる心をもりて をわりけむ。
命のきはに、言ふこともなく ゆきつきて
道にたふるる生き物のかそけき墓は、草つつみたり
まさにこれが人と馬が一体となった最後を如実に示している。馬頭観世音の碑がこれほど日本に多いのは馬と人とこのように一体として生活してきたからである。
旅の辻
黒羽の城跡に那須野を望む
なお刈り入れの人をよそに見て
秋の山影心にしみぬれ
右は太田原
左は馬頭
真っ直ぐは太子へ
秋の日さして
道はここに分かれぬ
馬頭町に我が行くことなし
いつの日か馬頭町に行くことあれや
馬頭観世音の由来の町
その名のみ我が心に残りぬ
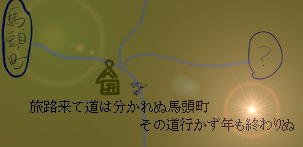
自転車で那須の原を行ったとき馬頭町で行けなかった。何かかなり遠い町に感じた。車だと簡単に行けるが自転車だと遠いのだ。電車の通らないところは車を持っていないものにとってはなかなか行けない所、不便な所なのだ。交通の便がよい所は遠くでも行ける近い所なのである。いづれにしろ馬頭町という名の町があるほど馬と密接に一体となり暮らした昔があったのだ。馬といえば野馬追いと馬頭町も馬に由来しているから関係あるといえる。