
 小林勇一
小林勇一
目次

航海の日々の夢9月21日(2003)
枯野の中の無人驛(新しいペ−ジへ)
一本松の春
ドイツの森の館
バラと雪
石と旅人
山道の藤の花
山陰の二つの石
須恵器の杯
庭のベルフラワ−
砂場の船 2004-3-27 砂場の王国を追加4月7日
 童話編に「砂場遊び三編」として「砂場の川と人形」を追加2005-10-12
童話編に「砂場遊び三編」として「砂場の川と人形」を追加2005-10-12
腰掛け石の語る昔 2004-10-1
冬眠に入る前の蛙の遊び 2004-10-21

一本松の春
冬の日、北風がその一本松にふきつけ松はただ一本淋しく耐えて立っていました、その田舎の田んぼの中に一本の松はいつも淋しく立っていました、まれにしか通る人もいない田舎の道の辺に立っていました、風の日も雨の日も黙って立っていました、冬の夜、静かに田舎の家の灯がともっていました、一本の松はやはり黙って立っていました、その下に小さな祠があり誰かが供えたものがありました、時に雪がふり春はなかなかきませんでした、しかし今日は晴れてどこからかあま−いなんともいえぬ香りが流れてきました・・・・・・
「ああ この香りは・・・・・梅だ・・・・」
近くの梅林の梅の香がふくいくと尽きず流れてくるのでした・・・・
「ああ この香りは・・・・・」
梅の香りはその一本松を満たし尽きることなく流れてくるのでした。梅林の香りは大変こい梅の香りを流して尽きることがなかったのです。一本松は今春を迎えて喜びにその梅の香りに十分に満たされていたのです。
「こうして一見何もないような淋しい所でもいいことがあるもんだ」
一本松はそうそっとささやきました。あえて幸福を求めなくてもおそらく幸福は思いがけなくどこからかやってくるものです。天地は恵みに満ちているもので神様は人を幸福にしたいと思っているからなんです神様は人を不幸にしよしとはしていません、人は人を不幸にしますが神様はそんなことを望んでいないんですから・・・・・
そしてぽっかりと流れてきたのは春の雲でした
ぽっかりぽっかり春の雲
ふうわりふわり一本松の上にきた
ぽっかりぽっかり春の雲
ふうわりふわり一本松の上にきた
「雲さん、春ですね、どこへ行くんですか」
「わかりません、気ままな風まかせですよ」
「梅の香りが流れてきてとても気持ちいいです」
「そうですね、あんなに一杯咲いていますから」
こうして春の雲はまたどこかへふうほりふわり流れてゆきました。そして一本松はささやきました。
「こうして動かずに立っていても訪ねてくるものはあるしいいことはある」
そして夕ぐれ時、今度は鶯の鳴く声が聞こえました、
「ああ、鶯もないた、美しい声でないた」
その声は一本松にひびき一本松は聞き入るのでした。
「うう、ここで一句わしもつくらにゃな
聞き入りぬ夕鶯の音色かな
どうかな、まあまあかな、」
こうしてまた一本松は田舎の田んぼの中に立っているのでした。




風車がまわる
くるくるくる風車がまわるまわる
風にそよいで今日もくるくるまわる
小さな庭にニチニチ草今日も咲いた
ひらひら蝶が舞い入り去った
ぶんぶんぶ−ん蜂もやってきた
蝉もまだニイニイニイ鳴いている
でももう秋が来たよ涼しい庭だ

ドイツの森の館
鏡の間の幽霊
旅人はどうしてかドイツの黒い森の奥深く迷い込んでしまった。そしてどこまで歩いたのだろうか、そこには古いア−チの石の門があった。
「こんな森の奥になぜこんな立派な門があるのか」
旅人はいぶかしがったがその脇には門衛のように一人の兵士が像として立っていた。剣を持ちなんと兜は黄金に輝き鎧を身にまとって威儀を正していた。その眼差しは鋭くその旅人に向けられていた。そのロ−マ兵はドイツ語で話しかけてきた。旅人はドイツ語を多少知っていたらしく片言のドイツ語で答えた。「おい、お前はどこから来たものじゃ」
「ええ、私は・・・ヤ−パンですが・・・」
「ヤ−パンじゃと・・そんな国は聞いたことないぞ」
「そういわれまして、困ります、パスポ−トもちゃんと持っています」
「どれ見せてみろ」
こうして旅人はパスポ−トをさしだした。
「これがパスポ−トか、これはここでは通用せんな」
「そんなこと言われましても困ります、これしか自分を証明するものがありません」
「お前の顔はゲルマニアでもケルトの顔でもない、見たことない顔じゃ」
「ヤ−パンです」
「そのヤ−パンがわからんのじゃ」
「ところであなた様はどこのお方ですか」
「わしをわからんのか、ロ−マの兵士だ、見ればわかるじゃろ」
「やはり、ロ−マですか、とするとロ−マの時代、日本は・・・国はなく縄文時代かな・・・・これでは説明しようがないな・・・」
「おいおい、何をつぶやいておるのじゃ 得体の知れぬもの」
「ともかく私はヤ−パンから来たんです」
「そんなものは地図にもない」
「そう言われましても」
そのロ−マ兵は確かにその迷い込んだ旅人に対してそんな風に話かけたのですがまた石の像となりその門の脇に立って口を閉ざしてしまいました。そこで旅人はまたその古びた一部壊れた石の門をおそるおそる入ってゆきました。
すると大きな館が目の前に現れました。
「これは立派な館だ、こんなところにこんな立派な館があるとは」
そこの館の庭も多少荒れてはいましたが広々として散歩の道がありました。その古い壁にはびっしりと蔦の紅葉が真っ赤になりおおっていました。蔓は何百年もそこに張り付いたように伸びていました。おそるおそるその館に入ってゆくと長い木の廊下はきしみ不気味でした。そこにはいくつもの大きな部屋がありその突き当たりの木の扉をギ−と開くと広いホ−ルになっていてそこもがらんどうでした。そこには古びた大きな鏡がいくつもありました。その鏡の間になんとなく歩いて時を過ごしていると黒い森は深い霧におおわれていました。そして時々ゴ−ンガ−ンゴ−ガ−ンンと古びた教会の鐘は地の底からでもひびくように陰鬱にひびいてくるのでした。
「ここは一体何の部屋だったんだろう」
「ここは華やかなダンスパ−ティが日夜開かれた所だよ」
「ええ、誰ですか、その声は・・・」
「私だよ、私はここの主だよ・・・・・」
そこにいたのは皺くちゃの腰の曲がった白髪の老婆でした。
「あなたはもしかして魔女では・・・」
「はは、そうかもね、魔女の秤にもかけられたことあったな」
「やっぱり・・・」
「ハッハッハッ・・・・」
その旅人はその異様な姿にぞっとしましたがここではそんな人が出てきてもをかしくないそういう雰囲気に満ちていたのです。するとその鏡の間から笑い声や話声が聞こえてきました。
「さあ、もっと踊りましょう、踊りましょう」
「はい、あなたはまことに美しい、夏の日の薔薇のように美しい・・・お手をどうぞ・・・・」
華やかな踊りの輪はいくつもできて華麗な舞いは絵のように繰り広げられていました。それは確かに夢のような一時でした。
「さあ、踊りましょう、踊りましょう」
「はいはい、何度でも」
「今日は本当に楽しいですわ」
「バラが咲いた、バラが咲いた、真っ赤なバラが私の心に咲いた、真っ赤なバラが、バラが咲いた、バラが咲いた、散らないバラが・・・・・・・・
あなたの顔は夏の日の薔薇のように輝いています、まぶしいばかりです」
「その歌は聞いたことないわ、いい楽しい歌ね」
「まあ、歌にもいろいろありますよ,フランス辺りではやっている歌でしょう」
「そうね、あなたは外国通だからはやりの歌をすぐ覚えるわね」
こうしてこのホ−ルは若い男女で一杯になりその踊りはいつまでもやみそうにありませんでした。霧はさらに深く深く流れてその森と館をつつんでいました。やはりゴ−ンガ−ンゴ−ンガ−ンンと陰鬱に教会の鐘はどこからかひびいてくるのでした。ところが霧はじょじょにはれてきて光がさすようになりました。その時踊っている若い男女の顔はくもり不機嫌になっていました。そしてますます光が強くホ−ルにさしこみ気がつくと人っ子一人いなくなってもとのがらんどうの部屋に戻ってしまったのです。
「みんなどこに行ってしまったんだろう、あれは幻だったのか、変だ」
やがて晩秋の短い日はすっかり暮れていました。そのホ−ルの鏡には外の月が映っていました。その鏡にはよく見ると確かに女性の顔が映っていました。その女性は自分の顔を見てうっとりするように何度も見つめ入念に化粧していました。それは確かに肌の色は雪のように白く輝き美しい盛りの女性でした。
しかし突然その女性の顔は消えそこにいたのはやはりさきほどの白髪の老婆でした。
「あれ、確かに美しい女性が映っていたはずだが・・・」
「あれはもう消えたよ、館の主は私だ、このババだよ」
「ええ、では踊っていた若い男女は・・・」
「あれは深い霧の時に一時昔を偲びなつかしんで出てくる幽霊さ」
「じゃ、ここは幽霊屋敷・・・」
「まあ、そんなとこじゃわな」
旅人はこうして一日ここのちょっと汚く古くなったソファで寝ることになりました。そして夢で幽霊が嘆く声を何度も聞きました。
「ああ、美しく若い日は余りに短い、余りに短い・・・
あっという間に醜いばあさんになってしまうだわ・・・
ああ 二度と若い美しい日は帰ってこない、帰ってこない
いくら金を払っても若い日は取り戻せない、たちまち白髪の老婆だ
ああ もう一度美しい若い日にもどりたい、もどりたい・・・」
その声は地の底からうめくように悲しくわびしくせつなく聞こえてくるのでした。教会の鐘はやはり時々ゴ−ンガ−ンゴ−ンガ−ンンとひびいてくるのでした。
森の館の庭 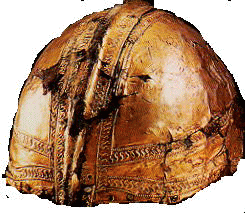
ゴ−ンガ−ンゴ−ンガ−ンンまた教会の陰鬱な鐘の音で旅人は汚れたソファから目覚めました。そしてきしむ長い廊下を歩み外の広い庭に出ました。そこに咲いていたのは赤い薔薇の花でした。枯れた古木や柳やちょっとした小径もある庭でした。晩秋で木の葉そこらじゅうに散っていました。今も一枚一枚はらはらと木の葉散り庭に積もってゆきます。その中に赤い薔薇は咲いているのでした。それはなんとういか真夏に咲く赤いバラとは違いちょうど古びた赤い絨毯のような赤でそれがなんとも心にしみる赤だったのです。何かににじむような赤だったのです。わびしい赤というか光の中に輝く赤い薔薇とは違っていました。
荒れたる庭に名残りと咲く赤い薔薇
館の主はなしになお咲きて赤き薔薇
はらはらと一枚一枚木の葉散りつもる庭に
昔を偲びて咲くやその赤い薔薇
教会の古い鐘の今日も陰鬱に鳴りひびく
この荒れた庭の壁にはびっしりと紅葉した真っ赤な蔦の葉でおおわれていました。その蔓はその壁にくいいるように這いい夕べのかすかなざしに浮き上がっていました。そこにはよく見ると人影が見えました。影は二人のようでした。そしてなにやらささやく声が聞こえました。
「私たちはいつもいっしょ、いつまでもここにいますね」
「そうですとも、私たちはいつも一緒、ここで暮らした日々があり
私たちはここを離れることはしありません」
「ええ 私たちはこの庭を愛してきたし愛しあった二人ですもね」
「ああ 夕日の光も消えてまた消えますよ」
この影は夕日の光の中と月影に現れて消える幽霊の影のようでした。幽霊はこの館にしろ庭にしろ思い出が深く離れがたくあったのです。
旅人はまた石の門のロ−マ兵の立っている所に来ていました。
「おい、ヤ−パン、まだいたのか」
「ああ ロ−マの大将さん」
「どうだワインでも飲まんかね」
「ワインですか」
「ワインを飲みながら語り合おうじゃないか、ここではなんだからそちらのモザイクの広場で座りながら語り合おう」
その門の道につづくようにモザイクの広場がありそこにはイルカに少年がのりイルカが盛んにとびはねているギリシャ風のモザイク画が描かれていました。そこに机と椅子が後ろの方から黒人がうやうやしく来てしつらえロ−マの大将の前に立っていました。
「ワインを、この方にも」
「ご主人様、わかりました、チャオ」
「あれ、チャオってイタリア人のあいさつだけどな」
チャオとはごづいのままにとか奴隷が主人に従う奴隷の言葉から出てきたものでした。スレ−ブとは奴隷のことですが例えばスラブ人は奴隷のことで一民族が戦争の結果奴隷にされたためそう呼ばれるようになった。ゲルマン人は強く奴隷にはならず後にゲルマン人はロ−マにも侵入し移動しロ−マを滅ぼした民族であった。奴隷の歴史はヨ−ロッパでも古いものでした。その黒人奴隷はギリシャの壷からワインを注ぐのでした。その杯は素朴なロ−マ風の鉄の杯でした。これは頑丈で持ち運ぶのにはいいものでした。すでにロ−マではガラスのグラスも作られていましたが持ち運びには割れやすいので向かなかった。
「この奴隷はアフリカから連れてきたのだよ、良く仕えてくれる、今や家族の一員ようになっている」
「奴隷が家族の一員に」
「そうでございます、とてもここのご主人様は親切にしてくれます」
「そうですか、奴隷というとあまりいい感じはしませんが・・・」
その頃奴隷にもいろいろあり家族に仕えた奴隷は家族の一員のようにもなり家族の一員として墓にも葬られた。それはカタコンベなどに残っている。検闘士にされたものや後の時代の大農場で働かせられた奴隷などはひどい仕打ちを受けたがこの頃の家族奴隷は知識階級や技術者など待遇が良かったのである。確かに奴隷の数は膨大なものでスバルタクスの反乱のように遂にはロ−マの驚異となりやっとのことでその反乱を鎮めたのだ。
「わしはアフリカでライオン狩りもした、象狩りもした。これも仕事だった。エジプトのナイル川を下って行ったこともある。ワニに襲われた時はびっくりした。エジフトにもそのナイルの上流までロ−マの威光は及んでいるのじゃ、地中海も船で渡ったこともあるし、灼熱の砂漠を越えて遠征したことも度々ある、アルプス越えて今ゲルマニアの地にいる、まことに歴戦のつわものよな、・・・・」
「まことにご主人様、ロ−マは偉大でございます、お世辞ではなく」
「そうだ、ロ−マ強いだけで偉大なのではない、公正な法の支配や建築技術、ラテン語や文字の普及、文化の面でも偉大なのだ。」
「そうでございます、ご主人様、強いだけではこれだけの国を治めることはできませんから」
「太陽がかたよりなくすべての国をてらすごとくフエアな法が必要なのだ、太陽はそれ故すべての国の上に輝きをまして君臨するのだ」
「さようでございます、強いだけではこれだけの大国を治めることはできません」
シ−ザ−のルビコン川を渡りしより
ガリア、ゲルマン、エジプト、アフリカ・・・
ロ−マの栄光の一翼を我はにないぬ
ロ−マは法により支配される
オリエントの王は過酷なる支配者としての王
その硬直した石の巨像は万民を奴隷として従える
ロ−マは市民権を得しものは法の下に平等
同等の権利は奴隷にも与えられる
ロ−マよ、永遠のロ−マよ、ロ−マの栄光は尽きぬ

「そうじゃな、ロ−マは偉大だ、すべての道はロ−マに通うずだ、さてヤ−パン、お前は一体何ができる?」
「私ですか、俳句など書いていますが、ヤ−パンの詩の一種です」
「お前は詩人か、ではヤ−パンの詩を披露してみたまい」
「理解されるかどうかわかりませんがでは
落葉踏みロ−マの門やゲルマニア
「ずいぶん短い詩だな、俳句は短い中に森羅万象を言い表すヤ−パン独特のものです」
「そうか、ヤ−パンも面白いな」
「どうじゃな、わしの奴隷にならんか」
「奴隷はいやです」
「奴隷といってもな、わしに仕えるということで自由が全くないわけではないぞ、それとも剣闘士にしてやるか」
「剣闘士、あのコロッセウムで戦う・・」
「剣闘士はお前には無理だ、ひよわそうだからな、ロ−マにはいろいろなものが集まってくる、その国も多様でお前も刺激を受ける、ロ−マは今唯一の世界都市なのじゃ、大きな図書館もあり知的刺激に満ちているのじゃ、ギリシャ人を先頭に、シリア人、エジプト人、ユダヤ人、アフリカのヌビア人やらアラブ人も来てきる、実に多彩ではないか」」
「たしかに魅力的ではあるようです、ヤ−パンだけでは小さい国ですから大きな詩や大きな芸術は創造できません」
「あっ、ご主人様危ない・・」
そんな話をしていると突然森がざわざわとしてビュ−ンと森の中から矢が飛んできてロ−マ大将の鎧に当たりましたが折れました。
「うう、これしき、またゲルマニアのやつらめ、しょうこりもなく抵抗してくる、手ごわいやつらよ」
こうして一時話は中断しましたが賊はすぐ森の中に消えて行ったようでした。
「こういうことはしょっちゅうあることだ、気にするな」
「ここはやはり戦場でしたね」
旅人もちょっとびくつきましたが賊も逃げたようなのでまた話しを続けました。
「それにしてもな、ヤ−パンという国については皆目見当もつかん、もしかしてセレスの国のものか、御婦人方が召される羅の肌ざわりのいい透けたような布はセレスとか言っていた、そのセレ−ヌという国はとんでもない遠い国で砂漠の商人がラクダで運んでくるとか、そのセレ−ヌの国のものでは・・」
「セレスとは確かにシルク、絹のことです、その国の近くなことは確かですが・・・・・説明するのがむずかしい・・・」
「何独り言を言っているのじゃ」
セレスヌとは中国のことであり日本は(JAPAN)漆器の意味だった。漆器で世界に知られたのがその名だった。その国は最初その国と貿易するものがその国の特産物をさす場合がままある。漆は縄文時代から日本にあり津軽地方のものが一番古いといわれるから歴史的にも日本の名が漆器から名づけられたのはうなづける。例えば他にルゼンチンは銀の国という意味であり銀を産出する故名づけられた。実際はスペイン人がラプラタ川で銀と交換した交易がありそう名づけられたが銀の産出はなかった。でも銀というのが世界貿易に大きな役割を一時は果たしたのだ。黄金より銀が重宝された時代があった。その後エルドラ−ド(黄金郷)が大陸発見の冒険の目的となった。
確かにシルクロ−ドを通じて中国の絹はロ−マにも達していたのだ。それは大変高価なものでロ−マの貴婦人のみが身につけられるものだったのだ。
「さあ、もっとワインを」
「私は酔ってきました」
「これくらいで酔うのか、わしも詩は知っている、松の木によりてバラの花を輝く髪に飾りシリアの甘松香を・・・・」
松はロ−マで好まれたものでバラはヨ−ロッパは象徴する花でシリアは異国の香りの漂うエキゾシズムがあった、つまり詩も自ずと国際的になるのがロ−マだった。あるロ−マの貴族は何カ国もしゃべってもてなし話題になったという。今でもそういう人はもてはやされる。マルチリンガルの時代なのだ。旅人はだいぶ酔ってうとうととしてしまった。
「飲みなれていないもので・・・」
「お前の国にも酒はるか」
「米から作る酒があります」
「米とは、麦からはビ−ルを作るが、米は知らんな」
「米は知らない、ロ−マの時代は米は知らなかったか?」
「ロ−マに行こう、ロ−マは偉大だ、ロ−マに富のすべてと世界の知識がある、ロ−マでお前の才能も十分に開花するのだ・・この門から石畳のロ−マの道は世界の都ロ−マに通じているのだ・・・そしてここにもマイルスト−ン立っている、ロ−マの道はブリタニアの果てまでもつづく・・」
「ええ、そうかもしれませんんん、ううう、ロ−マに行こう、ヤ−パンは小さい、小さい・・・・世界が今や舞台なんだ・・・・」
「おい、ヤ−パン、お前にこのコインをやろう、ロ−マの皇帝のコインだ」
「ええ、このコインを・・」
「我が皇帝アウグストスの顔の彫られたコインだ」
「これは立派なものです」
旅人はワインに酔いロ−マに心は向かっていました。そしてそこに酔い眠り込んでしまったのです。それからぐ−ぐ−疲れて旅人はどのくらい寝こんでいたでしょうか、時々うなされて声を出していました。
「奴隷はいやだ、剣闘士はいやだ、・・・・」
こうしてはっと目覚めた時、そこには同じようにロ−マの黄金の兜の大将の像が立ってをりイルカのモザイクの広場の上に寝ていたのです。そこからは石畳の道が森の中を真っ直ぐにつづきマイルスト−ンが古びて立っていました。マイルスト−ンはロ−マの道に建てられた一里塚のようなものでした。
「あれ、このロ−マの大将とずいぶん話したようだけど今は全くこの像の大将は口を開かない、夢でも見たのか、それにしても夢とは思えない生々しいものだった。落葉に埋もれてとぎれとぎれになっていましたがその門から石畳の道はつづいていました、そこで急いで街の方に旅人は歩きはじめました。
森の一軒屋
その黒い森の道の途中に枝をポキッと折った木があった。その枝の折った木は歩いてみると森に誘われるようにその枝を折った所を目印しに行くようになってしまった。その森からは鹿がピョンとはねてでてきたりした。また不思議なことに一本の杉の木のようなものにびっしりと赤い木の実がたわわになってをりそれを食べると甘くそれを何度もとってはたべながら歩いた行った。いくつもの枝の折れた木をたどってゆくと一軒の小屋があった。
「こんなところに誰が棲んでいるのか、人の気配はある・・確かに人がいる」その家の庭らしき所にいたのはこれまた白髪の老人だった。
「グ−テンタ−グ・・・・・・」
「あなたはだれ、ドイツ人じゃないね、イタリア人か」
「ヤ−パンです、・・・」
「ヤ−バンだと、そんな国知らんな」
「ここで暮らしているのですか」
「そうじゃ、ここが私の家だよ」
その家は薪を積んであって煙突もあり冬の仕度をしていたようである。鹿の皮がいくつか干してあったり鹿の角を飾ってあったりして畑もありここで鹿などをとって暮らしているみたいだった。
「私は森の中に迷い込んでしまったんです、そしてなんとか街の方に出ようとしています」
「街か、長い間行ってないな、そんなには遠くないんだが迷うとこの森はぬけだすのがむずかしいんじゃよ、まあここでちょっと休んでゆきなされ」
「ダンケ、どうもありがとうございます・・・・」
「なにか食べるものを用意しましょう、これは山の木の実の酒ですわい、飲んでみなされ パンにはこの木の実のジャムをつけなされ」」
「ああ、これは途中で食べた木の実かもしれませんね」
「そうです、これは森のコケモモですよ」
「そういえばそんな味が、ヤ−パンのとは違いますが」
こうして旅人はこの森の一軒屋でコケモモの酒とパンなどをごちそうになって疲れをいやした。ただこの黒い森の中でちょっと不気味ではあった。余り時間もなかったので急ぐことにした。
「そろそろ街の方に行きたいと思いますが・・・」
「そうかい、同じように枝の折れた木をたどってこっちの方を行きなされ、街の方への一本道に出るはずだ、このコケモモの酒を持ってゆきなされ」
「ああ、これはどうも、いい土産になります」
「ああ、それからな大事なことをい言い忘れた、この森には妖精が出るんじゃこの妖精は遊び仲間を探している、しつこく誘うじゃがあんまりかまわない方がいい、この森から出れなくなる、というのはこの妖精たちと遊んでいると時間がたつのが普通より早く気づいてみると白髪の老人になってしまうじゃ、人間というものどんなつまらぬことをしていても時間はあっという間に過ぎてしまうもんじゃよ、」
「そんな妖精が本では読みましたが・・・・・」
「ああ それからもう一つ魔女の塔には近づくな、どんな言い訳しても無駄だ、魔女にされてしまう、女だけじゃない、男も悪魔の手先として火あぶりにされてしまうぞ」
「火あぶりだって、それはひどいや」
旅人はその妖精のことや魔女の塔のことなど考えながらその森の一軒屋を去ってゆきました。
「はたしてそんな妖精がいるのか、そんな妖精が出てきてもをかしくない森だ、もしかしたらあの老人は妖精と遊んでいるうちあっと言う間に老人になってしまったのかもしれない・・・」
こうして枝の折れた所をまたたどってゆくと甲高い笑い声が聞こえてきました。
「ハッハッハッ、あそぼう、ねぇ、あそぼう、早くこっちへこいよ
ハッハッハッ、あそぼう、あそぼう、あそんでいかないとここを通さないよ・・・・・・・・・・・」
「だれだそこにいるのは」
その森の中から出てきたのは小さな妖精でした。何人かいたようです。
こうして妖精はいっしょになって道をふさいでしまいいました。
「急いでいるんだよ、私は、ちょっとだけならいいけど・・・」
「ちょっとだけでいいんだ、」
「よし、ちょっとだけだよ」
「じゃかくれんぼしよう 僕たち隠れるから探してよ」
「よし、わかった」
妖精たちはいっせいに森に散り隠れてしまいました。妖精たちすばしこく木のかげやら木のてっぺんにいたり穴の中にくぐったり見つけるのが大変でした。「こっちだよ、こっちだよ、ハッハッハッ」
「また消えたか、リスのようにすばしこくてつかまらんな」
「こっちだよ、ほら、ここだよ、ハッハッハッ」
「まてまて、ああ また逃げられた、早くてつかまらんよ」
妖精はまるでリスがかけるように木をするする登ったりあっというまに飛んで消えたり変幻自在でとてもつかまりませんでした。
「じゃ次はカケッコだ」
「今度は負けんぞ」
「よし 一列並んだ並んだ」
「ピィ− ヨ−イドン」
「う−ん、まけるもんかまけるもんか」
「あいよ、一番はぼくだ、」
「二番はぼくだ」
「三番はぼくだ」
「・・・・・」
「ああ、くやしい俺はピリだ」
「ハッハッハッハッ、ビリだビリだ」
旅人はくやしかったのでもう一回やろうといいました。
「今度はまけんぞ、まけんぞ」
「ヨ−イドン」
「ハッハッハッ、やっぱりおそいぞおそいぞ」
「ハッハッハッやっぱりピリだビリだハッハッハッ」
妖精たちはかけっこはあきたので森の家でチェスをやろうといいました。旅人はチェスはできましたがあまり上手ではありませんでした。
「チェスをやろうよ、チェスをやろうよ」
「ニ三回だけだよ、私は強くないんだ」
「かまわないよ、」
こうして森の妖精の家でチェスをやることになりました。」
「これはこうだな」
「う、それならこうだ」
「またこれも簡単に負けたな」
「もう一回だけやろうよ」
「まあ いいだろう」
「こうだ、」
「それなら、ええとキングはこうだ、ビショプはこうだな」
「よし、クエ−ンはこうだ」
「ああ、またまけた、もうチェスは終わりだ」
「もう一番だ、もう一番だ」
「うっ、もう一番だけだぞ」
「う、もう一番でいいよ」
「また負けか、今度は勝つぞ、なかなか面白いな」
「じゃ、もう一番だ」
今度は勝つぞ、今度は勝つぞ」
旅人はチェスが少しづつわかってきて面白くなってしまい、負けたくなくなりました。なんとか勝ちたくなったのです。でもそろそろ日が暮れそうになっていました。旅人はもう早く帰らないと街の方に行かないとまずいと思っていました。明るいうちに街の方に行かないとホテルに泊まれなくなると思い早く帰ろうとしていました。
「ここに泊まってあそんでゆきなよ、あそぶことは一杯あるよ」
「でも、早く街に行かないと・・・」
旅人は老人の言ったことを思い出していました。これ以上長いすると大変なことになる。森からもぬけだせずあっという間に老人となりここで木の実でも食って暮すになってしまうかもしれないとあせりました。
「もうだめだ、時間がないんだよ」
「もっとあそぼうよ、あそぼうよ」
妖精たちは旅人の手をとり足にからまりせがみ離れようとしませんでした。旅人はこれは危険だと思い妖精たちの手を振り切って逃げました。そしたら妖精たちは追っかけてきたのです。
「もっとあそぼうよ、あそぼうよ・・・ハッハッハッ」
その笑い声は森一杯に木霊してその笑い声がその逃げる旅人を追っかけとくるようでした。するとまもなく森の中になんとも陰気な塔が一つ見えました。
「あの塔は魔女の塔だ、間違いない、これはまずい、早く逃げよう」
するとまちかまえていたかのように魔女が道をふさぎました。
「逃げようとして無駄だ、魔女には神通力がある、逃げられないよ、おまえはどこからきたのかね、お前はドイツ人ではないね、ユダヤ人か、いや違うな、どこからきたんだい」
「私はヤ−パンです」
「ヤ−ハンなんてしらないよ、やっぱりこれは悪魔の手先だ、間違いない、逃がしやしないよ、魔女の塔まできてもらおう、そこでじっくり悪魔の手先かどうか調べるんだ、・・・」
「私は悪魔の手先でなんかありません、これは私のパスポ−トです」
「パスポ−ト、これはヤ−パンの証明書です」
「この証明書は本物か、にせものかもしれん」
「ともかく良くみんなで調べるから魔女の塔にきてもらおう」
「ええ、私はもう時間がないんです」
「時間はありあまるほどあるさ、なんでそんなに急ぐんだ」
「私は早く街に行かないと・・・」
その時旅人は決心しました。逃げることを決心したのです。一目散に走り出しました。無我夢中で走り出したのです。
「お−い、逃げるのか、逃げたって無駄だぞ、こっちは飛ぶこともできるんだぞ」
確かに魔女は飛んで追っかけてきたのです。旅人は必死で逃げました。黒い森の中から幸い遠くに明るい開けた所が見えはじめていたのです。その明るい所に出たら魔女は消え追いかけてきませんでしたがびっしょり汗をかいていました。その黒い森を出た所で牛の鳴き声が聞こえました。薪を積んだ農家がありその家の人に街の方に行く道をたずねました。
「街の方はどっちで」
「あっちだよ」
「ダンケ」
こうしてやっと黒い森をぬけ街の方を目指して早足で歩いて行くのでした。
」
アウグスブルグにて
さて旅人が着いたのはアウグスブルグの街でした。そこのホテルのドリトリ−に宿をとりました。そこには日本人もいたし外国人もいました。こういうところには今のような時代変わった人が必ずいます。
「バイクをロッテルダムにおいてきている、これから二年間バイクで世界一周だよ」
「ええ、バイクですか、それは大変だ」
その人はすでに50を越えていた人だった。そうした変わりだねはこの海外旅行ブ−ムの中で出てきているのだ。
「あなたはスペインから・・・」
「タバックはすおう」
「タバック」
「ああ、タバコね」
タバコはスペイン人が南米から持ってきたもので世界中に広がった。発音は世界中でタバコににてをり日本から韓国にもこの言葉は輸出された。日本経由で韓国、中国に輸出されたものもあるのだ。
「スペインのあいさつは」
「ボンゾウ−ル」
「ああ、フランスがボンジュ−ル、イタリアがボンジョル−ノ・・・・やはりにていますね ボンという都市の名もそこからきた・・」
「グランディ」
「ああ、グランディはすごい、立派だ、英語だとグレ−ト、これもにてますね」
そこにイタリア人が会話に入ってきました。
「私はどうもフランス語とスペイン語はわかりやすいのだがドイツ語は苦手だ・・・」
「ドイツ語はやはりラテン語系統とは違ったものなのでしょう、発音からもわかりますから、英語はもともとドイツ語をもとにしていますから親と子のような関係です、英語は他にハイキングの侵入で征服されたりフランスに征服されたりでいろんな言葉が交じり合った言葉ですね」
「そういうことかも、そこに一つの壁ができている・・・・」
その近くに英語をしゃべる人がいたのだがその英語がまたイエスをノイと聞こえたり普通の英語の発音と違っていた。どこの人かわからないが英語でもいろいろあり発音が変わってくるのだ。ヨ−ロッパの言語地図は複雑である。
旅人は街の方を散策することにした。街の市庁舎のある前にはロ−マの皇帝、アウグストスの騎馬像があった。アウグスブルグはこのアウグストスに由来している。街を見てまわるうちに博物館に入った。そこにはロ−マ時代のものが飾ってあった。その一つに黄金の兜があった。ロ−マの兵が身につけていたものだった。
「ああ、これは森の館の石の門に立っていたロ−マの百人隊長がかぶっていたものだ、するとあの兵は・・・・」
こうして一通りロ−マの発掘物を見て街の中を歩いた。ショ−ウインドウに古いバイオリンが飾ってあった。ここではバイオリンも作っているらしい。バイオリン作りもここでは古く伝統の仕事であった。それから店で絵ハガキを買おうと思いポケットから小銭を出した。
「これください」
「これは、なんですか」
「ああ、これは今の金じゃない、別な方だ」
旅人がポケットから出したのは見たことのない古い金でした。
「この金は一体どうしてここに・・・」
その金にはロ−マの皇帝の顔と馬に乗ったロ−マ兵が彫られていました。
「これは確かにロ−マ時代のコインだ、おそらくこの皇帝はアウグストス・・とするとあの森の中のロ−マの大将がくれたものだ・・ということは夢の話ではなかったのか????」
それで旅人は確認するために調べてもらため街の骨董屋に行ってみた。
「これはロ−マ時代のコインでしょうか」
「うう、これは・・・」
「どうでしょうか」
「ううう、これは確かにロ−マ時代のものだ、うう、これはレプリカではない、これをどこで・・」
「レプリカというと・・」
「この世界はにせものが多い、そっくりに同じものを作り売りつける」
「拾ったんです」
「これは値打ちものだよ、博物館にしか飾れないものだ、売ってくれないか」
「いくらで」
「1000マルクでどうだ」
「1000マルク・・・そんな値段が・・」
旅人は驚きました。本物であることがわかったからです。旅人はおみやげに日本に持ってかえることにしました。この街にはまた有名な豪商がいて財を築き大きな館を持ちそこではダンスパ−ティが日夜開かれたそうです。ロ−マから免罪符を運んだりしてもうけたというから大変な数の免罪符を売られたりしていたのである。それとここがアルプスを越えてゲマルニアと結ぶ通商路になっていて栄えたことがわかる。あれこれ考えてみると森の中のことはまるっきり夢ではない現実のことと思うようになりました。そしてまたぶらぶら歩いていると公園にロ−マ時代の遺跡から発掘されたものが並べてありました。その石のレリ−フに松の実がありました。ロ−マの兵を浮き彫りもありました。このアウグスブルグの街の紋章は松の実でした。松は南国のものでロ−マ人が好んだものでした。こうしてみると森の中の夢を証明するかのようにロ−マ時代のものが陳列されているのでした。旅人は落葉を踏みまたホテルに帰って行きました。まだ旅はアルプスのスイスとつづくのでした。



バラと雪
遠い晩秋の田舎の駅にバラは人知れずひっそりと咲いていた。バラは誰を待っていたのだろうか、そのバラに気づく者もないほどだった。しかし確かに誰かを待っていた。
「今日も来なかった、汽車はまた去っていった、私をふりかえるものはない、吹いてくるのは今日も冷たい風、ああ 私はこうしていつまで待っているのだろう」
確かにそのバラの花に注目するものはありませんでした。しかしバラはひっそりとつつましく美しく咲いていたのです。けして文句も愚痴も言うことはなかったのです。そして季節は晩秋から冬になっていました。
同じように人は乗り降りしても遠くから汽車がやってきてもやはりそのバラのもとに降り立ちそのバラに注目する人はなかったのです。そうしてやはりバラは遠い田舎の駅にひっそりとあまりにひっそりと息をひそめるように咲いていたのでした。
そして寒い日が続いたある日のこと天から雪がひっそりとふりそのバラの花につもったのです。
「ああ これはなに・・・・ああ 白い白い雪だわ・・・清らかな雪ね、私に触れたのはこの白い清らかな雪だけ、ああ 気持ちがいいわ、とても幸せ・・・・・・」
バラはこうささやいて雪の中に咲いていました。天からこのバラに贈られたのはこの白い雪ででした。このバラにふれたものほかにありません。そのバラはここに人知れず咲き氷の華のように水晶のように近寄りがたい静粛な美をたたえ咲いていました。それはまるで美しい心が結晶したように咲いていました。そのようにあまりにふれがたく美しいものでした。しかしそれに気づくものはなっかったのです。
「ああ あそこに美しい花が咲いているな、あの花は特に美しい、あの花は私がもらおう、人の汚れた手にはふれさせたくない、私の側に置いておこう」
こうしてこのバラは神の手元に取り去れて消えました。しかし誰もその花のことは咲いていた時も知らなかったのでその花の消えたことも知る人はなかったのです。そして神様は一人つぶやきました。
「人はこの世をかえるだとか、理想の社会を作るだとか、人をせきたて騒ぎ立て努力するものにろくな者はいない、彼らは実は自らの欲に働く呪われた者、サタンの手先、このもっとも美しい私が造り置いた花に目もくれない呪われた者、私はここにすでに人の手では作り得ない、最も美しいものをここに置いているのに目もくれない、人はこれをまず見出し賛美すべきなのだ、しかしいつの世もそうだった、このように花は無視されて咲いていたのだ、世の多くが求めるものはこの一輪の花にはあらずこの世の欲と栄華がすべてなのだ、それ故にこの世はサタンのものでありこの世に私は呪いをおいたのだ」
神様こうして深く嘆息しその一輪の氷のように結晶したバラを見つめていました。
神の御旨に逆らわず
神の御旨のままに咲き
神の御旨に従順に
そはその美すら意識になくば
おごり高ぶることもなく
神の御側につつましく
汚れなく咲きて仕えぬ

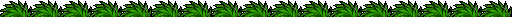
石と旅人
山には春がやってきました。そこかしこ桜が咲き鶯が盛んに鳴いていました。そんな道の辺に一つの石が春の日ざしにぽかぽかと気持ちよくしていました。そして独り言をつぶやきました。
「ああ、寒い冬もようやく過ぎて春が来た、春の日はあたたかく気持ちがいいな、さてこんな山の村だけど誰かこないかな」
「来ますよ、来ますよ、山の向こうの町からやってきますよ」
「ああ、ツバメさんですか」
その時その石の上をかすめるようにツバメが飛んで言いました。
「私たちも海をこえてはるばる飛んできたんですから」
「それはうれしいな」
ぽかぽか春の日はその道の辺の石をあたためていました。そして石は遠くに重なる春の山をながめていました。すると確かに誰かがやってきました。
「ああ 疲れた 疲れた ここに休むか あの峠はきつかった」
一人の旅人がその石の上に座り休みました。
「ああ ツバメさんのいうようにやっぱり町からやってくる人がいた」
旅人も大分前ですがここに来たことがあったようです。
「またこの石がここにありここで休む、俺が休むためにこの石はあるのか」石はその旅人が前にも来たことを思い出したようです。
「ああ また来ましたね、そうですよ、あなたを待っていましたよ」
そう石は言いましたが聞こえなかったようです。
旅人はまたたってその村を回り遠くの山を望み道の標識を見ると都路へ20キロとありそれを見て
「今回は遠いから都路は次に行こう」
といいその道をひき返し自分の住んでいる町の方へ帰ってゆきました。
そしてどうどうと春の水が勢い良く流れが交わるところの橋の上にバスの止まる標が一つぽつんと立っていました。それには塩浸と書いてありました。それで旅人は思い出しました。
「これが塩浸か、なるほどな」
旅人はうなずくようにその塩浸の名を一人口ずさんでいました。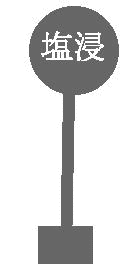
旅人はこの塩浸の謂れを聞いたことがあるからです。
「ここは昔は橋がなく塩を運んでいた馬が荷が軽くなるとここにわざと塩を落として軽くして水に浸した。そして三春藩へ運んだ。ここは相馬藩から三春藩や二本松藩までも塩を運んだ道だ、相馬藩は六万石、三春藩は五万石、その境でもあった、確かにそんなところだ・・・でも馬がそんなこと考えるかな、やはり相馬から三春は馬でも遠いし運ぶのがつらかったことは確かだな・・・」町からきた旅人は一人うなずきまた暮れかかる山道を行くのでした。今でも馬の苦労を偲んでか馬を供養する馬頭観世音の碑はたくさんあります。バスはここも一日ニ回くらいしか来ませんでした。
途中また道の辺に弁慶石と記された石がありました。
「さてさてこんなところにも弁慶がきたのか」
義経と弁慶にまつわる話は各地にたくさん残されていますから珍しくはないのですが旅人はここにはないと思っていたのでしげしげと見て去って行きました。そして夕べ帰るが鳴いていました。
「そろそろカエレ、そろそろカエッテくるな」
確かに山の家には山の学校から子供が帰ってきたようです。そして石は春の日永の夕べ一人もの思いにふけっていました。旅人が一時立ち止まり見ていた標識にぼんやりと見える字がきにかかっていたのです。その時ツバメさんが飛んできたので聞いてみました。
「ツバメさん あの道の標識に書いてある字は何ですか」
「ああ 見てみましょう」
ツバメはさっと飛んでその字を見てすぐに戻ってきました。
「あの字は都路という字です」
「都路ね、それにしても都路とは何だろうな、確かにあの標識は都路とある、都路へつづく道なんだ、でも こんなところに都がどうしてあるんだ、こんな山の中にだよ 何にもない山の中にだよ」
こんなところに都がどうしてあるんだ、こんな山の中にだよ 何にもない山の中にだよ」
「石さん、石さん、都路は昔々天皇様がお通りになった道なんだよ、実際ここには天皇の子孫だなどと言う人が住んでいましたから」
そう言ったのは枝垂れ桜さんでした。
「ええ、天皇様だって、それは大変だ、それで都へ通うじる道だと、なるほどなるほだ、合点、合点、枝垂れ桜さんは物知りだ」
「ここにこうしているのも長いですから」
「それはお互い様ですが 都路はいいですな、一度は行ってみたいですな」
「本当に行ってみたいです」
そうして道の辺の石と枝垂れ桜は遠くの暮れてゆく春の山と都路へつづく道を見ながらひっそりとまた静まってゆくのでした。鶯もまだ気持ち良く鳴いていました。
すると桜の花びらが音もなくはらはらと散って花びらが小さな道を作りその道がまるで都へ通じる都路となっていました。
「あれ 桜の花びらが散って都路になった うう やっぱりここは都路へ通じる村だ」
その桜の花びらの道を今度は細い山の月が照らしていました。山の桜も今年もはやくも散ってゆくようです。道の辺の石はやっぱり遠くから来てここに休んだ旅人を思ってまた静かな眠りにつきました。そのわきに古木の枝垂れ桜は長々と垂れ咲いていました。


山道の藤の花
その山の道は通って行く人は本当に少ないのでありました。この坂を越えれば山の村はありましたが人が行くのは一日何人といほど少ないのでした。
風にぷらりぷらぷら藤の花
この山の道行く人まれや
一日ぷうらりぷらり藤の花
その藤の花に誰かが話しかけてきました。
「藤の花さん、藤の花さん、今日は誰がこの山道通りましたか」
「ええ だれですか、ああ お月さんですか あなたがいたのですね」
「いましたよ、いましたよ、・・・・」
「誰が通っていったですって・・・誰が通ったか・・・まあ 何人かは
通りましたよ、覚えていませんよ 私は関所の役人でもないですから」
「まあ まあ そう怒らずに 誰が通ってもかまいませんよ」
「そうですよ、あなたも無用の暇な方ですね」
「あなたも そうして風に吹かれてぷうらりぷらり 暇な方」
「おたがいさまですね でもこの道を行く人は少ないにしろ毎日働いている人ですよ、ごくろうさんというくらいいう気持ちがあってもいいのでは・・・」「まあまあ よくいいますね あなたのようなこの世とはまるっきり関係なくぽっかり浮かんでなんにもしないでこの世をながめているばかりの・・」
「まあ そうしたらおたがい重苦しいものになりますよ おたがい責めるのはよしましょうや」」
その時一羽の黄色い蝶がその藤の花にとんできてまつわりました。
「蝶さん どこへ行くんですか」
「どこということはない、山越えた向こうの村にでも」
「山の向こうに村があるんですか」
「ええ ありますとも 幸いの村がね、山のあなたに幸いが住むという村がね」
「なるほどね、山の向こうにも村がありますか、それはいい、行ってらしゃい」
「行ってきます」
黄色い小さな蝶は一瞬まぶしく光り藤の花にまつわりまた風に流されて山の向こうの村に飛んで行きました。そして藤の花やっぱりのんびりと風にふかれて垂れているだけでした。
風にぷらりぷらぷら藤の花
この山の道行く人まれや
一日ぷうらりぷらり藤の花
お月さんがぽっかり光りさみしい山の道は今日も行く人も本当に少なく暮れるてゆきました。そして蛙が鳴いていました。
「山の向こうにも村がある、ケロケロケロ
山の向こうでも仲間が ケロケロケロ
山の向こうの村にも行ってみようや ケロケロケロ」
その蛙の鳴く声は向こうの村にもひびいていったようです。
そして夜になり月が明るく山の道を照らしていました。そしてお月さんは輝き出したお星さんにささやきました。
「この道を確かに人が今日通りましたね、くっきりとその人の影が残影としてこの淋しい山道を行くのが見えます」
「ええ、確かに人の影がゆっくりと行くのが見えます」
その人影はいくつかの坂をこえ曲がる道を行くのでした。そしてなぜか分かれ道でその人影は歩みを止めました。
「どっちの道をゆくかな 右か左か・右は小宮 左は・・・・」
そこは淋しい山の村の別れ道でした。人の影はさらに山の道を移動して行きます。
「ここは二枚橋、家はニ三軒・・・・・」
その人影は独り言をいいつつさらに淋しい山道を移動してゆきます。月はこうこうと明るくその先を照らし出していましたので道に迷うことはありませんでした。
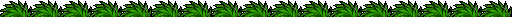

山陰の二つの石
その山陰の道は通る人は本当にまれだった。その道に二つの石があった。冷たい風がひゅ−ひゅ−その石に吹きつけた。辺りにはまだ雪が残っていました。二つの石は何かささやいていた。その声は普通の人には聞き取れない、ささやくような声だった。ここはいつもしんとして淋しい場所だった。何故なら山陰になっているから日がかげりやすいのだ。聞こえるのは清らかな流れの音と風の音だけだった。
「風がつめたいな」
「ああ 春はまだだな」
「う−ん また寒のもどりだ」
「しんぼうだよ」
「そうだな 桃栗三年、柿八年、実になるには時間がかかる
急いでも実らん、しんぼうがないと実らん」
「ああ こんなところで何の実りがあるかというがよ、神様はどんな場所でもそれなりの実りの場所として与えてくださっているんだ神様が作った所には無駄な場所はないはずなんだよ」
「そうだよな、不満を言ってもどうにもならんよ、しんぼうが大事なんだよ、しんぼうすればいつか花も咲き実もみのる」
「う−ん 俺達はもうここをどれだけの歳月ここを動かないでいるか、それをつまらんと自由に飛ぶカケスが言っていたけどな、動かないでもここはいいところだな」
「う−ん 何より静かなことがいいな、今の世の中騒々しすぎる」「そうだな、ここの静けさは乱されたくない」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ここで話はしばしとぎれてまた二つの石は黙ってしまいました。風はまたひゅ−ひゅ−と吹きつけ辺りには人影もありません。石は確かに黙ることが得意です。神様から黙ること沈黙することを言いつけられたようにその長−い長−い歳月をほとんど沈黙していたのです。こうしてまたささやくように聞き取れないような声で二つの石は話始めました。
「大事なことは口をつぐむことだ、無駄なことをぺらぺらしゃべってはならん」
「ああ 人間はしゃべりすぎるんだ、口から生れたようにしゃべりすぎるんだ」
「ああ 口は一番の災いの元だ、口をつつしむこと沈黙することは実にいいことなのだ それだけでこの世は平和になるんだ 」
「まったく 人間がくるとうるさいんだよな 人間がしゃべると空気さえ汚れるんだよ」
「う−ん まったくだ ここにさえづる小鳥の声は美しくひびく、ここにはそれしか聞こえてこない、なぜか俺達はかたく口を閉ざして沈黙しているからその小鳥の声も一段と美しく聞こえるんだ、人間が来たら騒々しくて小鳥の声もだいなしだ」
「ああ まったくだ 山でも木でもみな沈黙している 人間だけだ、あんなに騒々しいのはな」
「口をつつしむ 黙ることは偉いことなんだ 無駄なことを言わないから賢くなり偉くなるんだ 馬鹿でも黙っていると偉そうに見えるようにな これが簡単なようでむずかしいんだ」
「ああ 人間で嘘つかない人がいないように 嘘つかないで沈黙していたらその人は聖者だ」
「そうだ 俺達はいつも口をつぐみ不満や愚痴も言わない、嘘もつかないから聖者だ というよりは沈黙の修行者だ
」
しんぼうの木に花が咲き実がみのる
しんぼうのあとに喜びがくる
しんぼうするのは日々のつとめ
それぞれしんぼうして花が咲き実がみのる
こうしてまた二つの石は黙ってしまいました。その山道を今日通ったのは二人だけでした。この山に住んでいる人でした。あとそこに聞こえるのは清らかな流れの音と風の音と小鳥の鳴く声だけでした。そしてまたささやく声がしました。湖小手は大きな声をあげることははばかられるようにささやくことしかできないように静かな所だったのです。
「しんぼうだよ、まもなく春はくる、しんぼうしたらいつか実りもある」
「ああ しんぼうだ、しんぼうがなければ何もならん 災いはしんぼうしないから起こるんだ しんぼうすればいつか開ける道もだいしにしてしまうんだ 災いはみんなしんぼうしないからだ」
「一年くらいで金持ちになれるか、偉くなれるか、何物かになれるか とうてい無理だよ」
「ああ 俺達はどれくらいここに黙る修行しているか それを考えてみろ」
「まったく しんぼうせずに実る物はねえよな 一攫千金などこの世にはねえ ここに金を求めてきてもなにもねえがな」
「清らかな水の流れの音、小鳥の歌、そして春には花が咲く・・・」「それで十分だな」
「でもここにも自動車通るようになるんだってよ」
「ああ もう工事はじまったよ」
「ここもうるさくなるのか 自動車はいやだよ」
「あれは便利な物だがどこでも沈黙を壊してしまうんだ」
「ここの沈黙も壊されるのか 人間はどなんところにも所かまわず騒音をふりまき神聖な世界を壊してしまうんだ」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
その二つの石には冬の薄い午後の日がさし人影もよらずまた黙ってしまいました。春も近く一時あたたかい風が吹くことがありましたがこの山陰の道はかなり高い所にあり寒いのでした。さえ返る月が山に光っていました。
それからようやく春がやってきました。その二つの石のかたわらにはまるで残雪のようなキクザキイチゲの白い花がよりそうように咲いていました。二つの石は幸福そうにやはり黙っていました。すると盛んに小鳥がその石にとまり春の歌を声の限り歌いはじめました。石は気持ちよさそうにその歌に耳を傾けていました。清らかな流れも気持ちよくひびいていました。
そして真っ白にコブシの花が咲き風にゆれていました。その花やがてはその二つの石のところに散るのでした。二つの石は沈黙して花をながめ小鳥の声を聞き清らかな流の水の音を聞き黙っているのでした。沈黙しているから花も一段と美しく小鳥の声も美しく聞こえるのでした。ここは神の棲む場だから乱してはいけないのでした。人間は余りにも神の棲む場を乱して汚してしまったのです。いづれ神の怒りはきます。神聖な場を汚しつづけてきた人間は神聖な場から追放されるのです。この石には神が座りここは神が歩み通る神聖な場所だったのです。
ここに変わらず
声もなく
まことの契りを
交わすごとく
ここにありしを
残る雪
清らかにして
さえずりの音に
ひびく流れや
また訪ねきて
心鎮まる
この山蔭に
世の喧騒を知らず
声をひそめて
また暮れぬ
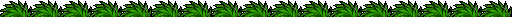
須恵器の杯
韓国の慶州は昔は新羅の都として栄えた所でした。日本で言えば奈良のような所でした。その名残が今でも街の真ん中に王様の墓がいくつも山のように築かれたことでわかります。慶州は今春の盛りでした。桜が千本も植えられて花盛りでした。連翹もまばゆく明るい春の日に輝いていました。四方に春の山が映えて当時の栄えた都が偲ばれました。この都も回りは日本と同じ田んぼでした。農家もありました。その春の田んぼの下から何か音が盛んにしたのです。
チャラチャラチャララチャララという金属的な音でした。
「お−い、酒をもっともってこい、酒だよ、カチャカチュカチャ・・・・・」
「はいはい、今もってまいります」
「百済は大和とと結んでいる、どうしてもたたかねばならんな」
「高句麗との関係もむずかしい、唐に援軍をたのむ」
「唐が味方につけば千人力じゃの」
「大和はまだまだ野蛮な文化のない国じゃよ」
「そうですな、我々がずっと豊かでですな、我々がいろいろ教えてやっているんですよ」
「それがうぬぼれてな、唐への朝貢で新羅より上にたとうとしたんですよ、全くうぬぼれてはこまる」
「まあ、唐が味方すれば一気にその傲慢な鼻ぱしらをへし折ってやりますわ」
「でもな、唐には頭が上がらなくなるな」
「ううん それもやむをえん、大和にはどうしても負けたくない」
「そういうことそういうこと チャラチャラチャララチャララ・・・酒だ、酒だ」
「はい、どうぞ おもちしました」
大和には負けられぬ
大和と結ぶ百済よ
我々は討たねばならぬ
新羅の栄えのために
大和には負けられぬ
・・・・・・・・・
こんな声が田んぼの下から聞こえたのです。新羅は大和とはいろいろ対抗していたのです。百済は大和とは深い友好関係にあり応援していたのです。でも唐との戦争で船を出したのですが白村江の戦いで敗れ百済の人々は大和に逃れたのでした。その中には百済王という人が日本の歴史書にその名を残しているのです。陸奥に黄金をとりにきた人は百済王の一族で奈良の大仏は金箔をぬられ輝きました。天皇はそのために百済王に位を授けたのでした。慶州にも仏国寺という奈良の大仏と同じ寺がありそこには華美な百済の塔とシンプルな新羅の塔が対を成して立っています。百済と新羅がともに仲良く栄える願いでもありました。
さてその後も何回もカチャカチュカチャと音がしたのです。農家の子供がその音を聞いて不思議がりその田んぼを掘ってみました。そしたら陶器の器の半分くらいのものがでてきました。
「アジモニ、これ何だい」
「ああ これはスエキの酒の杯だ」
「これで酒飲んだのか」
「昔ここに住んでいた偉い人たちが使ったものだよ」
「これをふると音がするよ」
「そうやって音をだし王様に仕える女性に酒をつがせたんだよ」
「はあ そんなもんか おもしれえな」
「それそこに飾ってある馬もその後ろに杯がついているんだよ」
「これかい、これが杯か、おもしれえな ハッハッハッ」
馬にのる人がいてその後ろに杯がついているものもあったのです。この須恵器は日本のいたるところでたくさん発見されているしスエとうつく地名はこの須恵器が発見された所で大量に須恵器が作られた所でもありました。これは土器と比べると鉄の様に硬くて薄く軽いのでこれを手にとった大和の人々は驚いたでしょう。韓国から古代にはいろいろなものが入ってきたのです。この須恵器もその一つです。
この慶州には大和の使いも海を越えてやってきました。それはそれは大変な苦労の旅でした。あるものは途中で死にました。壱岐の島という小さな島にその人の墓がまだ残っているそうです。今でも新羅にゆきたい新羅に行きたいというつぶやき無念の声がそこから聞こえてきます。
しかし新羅の都だった慶州も一日強い風が吹き千本の桜はたちまち散ってしまいました。それは強い風でした。春も終わりとなってしまいました。慶州は巨大な山のような王様の墓を残して今年の春も終わりとなるのでした。
でもまだ農家のあのスエキの杯を掘り出した子供は寝床でしきりにチャラチャラチャララチャララという音が聞こえてしょうがなかったのです。
「酒をもっともってこい、チャラチャラチャララチャララ」
「はい,どうぞ酒をもってまいりました」
「大和など一気にやっつけてやるさ、生意気な」
「チャラチャラチャララチャララ・・・・酒もってこい」
このチャラチャラチャララチャララ・・・・という音はこの新羅の都からはなかなか消えないかもしれません。なぜならたくさん須恵器はこの都の下に埋まっているからです。三一代も王様がつづいた都です。王やその家来はここになお昔を偲んで住んでいるのです。ここにはたくさんの日本人もきて昔を偲び日本へ帰ってゆきます。須恵器は今も作られてをりお土産に買ってゆきます。韓国は日本にとって一番身近な国なのです。

後ろは酒をつぐところだった。前には角がでている。
なぜここに角がでているのか。つまりこれを作った人がなぜここに角を作ったのかということである。この角はどこからヒントを得たのか、犀というのはすでに中国では知られていた。中国から伝わったのかもしれない。???


庭のベルフラワ−
田舎の町の一隅のとある庭にリンリ−ンリンリリ−ンとかすかにかすかにベルの鳴るような音が聞こえました。しかしその音に気づいた人はありません。あまりにかすかだったからです。その家の庭にはいつも雀が何羽か必ずやってくるのでした。それはいつもそこのおばあさんがそれも90近くになるおばあさんがパンクズを塀の上に置いておくから毎日それを食べにやってくるのです。
その雀たちが話していました。
「おい、あそこのいつも行く庭から何か聞こえないか」
「何かって」
「ベルの鳴るような音らしい」
「そうかな、そんな音聞こえないな」
「よく耳をすまして聞いてごらんよ」
「う−、そういえば何かかすかに聞こえるな」
「リンリンリリン−ンリン.........」
「あれはベルの音だよ、確かに」
「そういえばあの庭に石があるだろう、その脇に紫の小さな花を植えた、その紫の小さな花が一杯、ベルようなかわいらしい花だよ」
「う−そう、確かにベルの花だな、あれは・・・・あそこからよく耳を澄ますと聞こえるんだよ、ベルが鳴る音が・・・・」
「澄んだ音色だね、いい音だ」
こうしてピ−ピ−ピ−チクピ−ピ−ピピ−ピ−チク雀はおしゃべりしてバンクズをついばみ去ってゆきました。
そのあとに黙っている石のかたわらにそのベルの花は咲きその石も聞いていました。
「ああ、いい音色だ、とてもいい音色で気持ちいい、.....ここにもようやく春がやってきたな・・・」
そして石はまたし−んとして黙ってしまいました。冬の間庭は北風に吹かれ雪がつもりみぞれにふられじっと耐えていたのでした。そして春になりいろいろな花が咲き始めたのでした。
こうしてその小さな町の一隅の庭には訪れるものなく暮れてゆきました。その家を訪れる人はほとんどここ数十年見たことがないのです。雀は来ていましたがその他人が訪れることのないひっそりとした家でした。
夜になり月がでていました。月の光が庭にさしこみお月さんはつぶやきました。
「何かかすかに聞こえるね、あれはなんの音かな、ああ、あそこの狭い小さな庭かららしい、ああ、花が咲いているね、紫のベルの形をした花がね、あそこから聞こえてくるんだ、いい音色だ、この町はまだ静かだからいい、ゆっくりとベルの音に聞き入ろう.....」
月はやさしくその庭を照らしそのベルの花の鳴らすかすかな音に聞き入っていました。
しかし本当にその音色に気づいた人はありませんでした。その花はまるで誰も訪れることのない山深くに隠されて咲く花のようでした。確かにその花の一塊を手にのせて微笑んでいるのは森の神様だったのです。
それはなかなか人目にふれないしまたそのかすかな音を聞くものは少ないのです。


小林勇一
童話編に「砂場遊び三編」として「砂場の川と人形」を追加2005-10-12

小林勇一
童話編に「砂場遊び三編」として「砂場の川と人形」を追加2005-10-12
こんなところに都がどうしてあるんだ、こんな山の中にだよ 何にもない山の中にだよ」