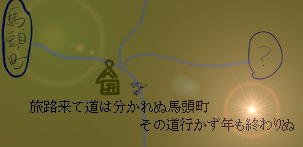旅の喪失(距離感の欠乏)小林勇一作
●塩尻の意味
ある土地のことはなかなかわからない、例えば塩尻でどういうわけかあそこから自転車を送って帰ってきたことがある。塩尻は実は豊橋とか糸魚川とか太平洋側から日本海側から塩が集まる、塩が達する尻だからendだからそうなづけられた。これが今まではわからなかったのだ。これがわからないことは旅行して塩尻に行っても何もわからない、第一塩尻ということ自体わからないのだから。塩尻は塩が集まる交通の要所だったのである。今でも汽車の路線や道の交叉する要所である。鉄道とも一致して塩尻は交通の要所である。旅をしてももし塩尻の意味すらわからないとしたら何もわからないのだ。なぜ地理が歴史がわからないかというと昔のように歩く旅をしていないからその距離感とかがわからない。
急行で行っても自動車で行っても早すぎるから塩尻の意味もわからない、これが豊橋とか糸魚川とか江戸とかから塩尻まで行ったら全然違ったものになる。その途中もわかるし塩尻まで行くことがかなりの旅になるのだ。急行で一時間という時間はその間の人間的歴史的感覚を麻痺させてしまう。距離を縮めただけで旅をしたことにはならないのだ。「ああ、やっと海から塩がここに到達した、運ぶことができた、・・・・」という昔の距離の感覚でてこない、地図をみれば塩尻は確かに太平洋側と日本海側から中間の地点にある。他にも塩尻はあるがあそこは四方からの塩尻、塩のタ−ミナルにふさわしい場所だったのだ。
●遠いからこそ都
汽車はそうした自然の道を歪める。阿武隈高原は汽車が相馬からは汽車が通らないから岩沼から福島と遠回りになる。これは自然から考えると極めて不自然なのだ。歩いて行く時代なら岩沼までわざわざ行ってそれから福島に来るようなことは誰もしない、まず阿武隈高原に出てそこから二本松とか三春に行くのだ。だから山木屋は塩の道の交差点であり栄えたことがわかる。仙台は相馬からはずっと遠い所であった。道をたどり歩くことが旅の基本である。その道が汽車の道になったとき旅はつまらないものとなった。道は未知であり道はいくつも別れてありそこに追分が別れ道が重要なものとなった。人が出会い別れる道であった。文字通り人はそこで出会い別れて二度と逢うこともなかったかもしれない、そういう切実な別れの道でもあったのだ。つまり距離感がなくなる旅は旅ではない、ここから江戸まではどれほど遠かったか歩いて往復してみたまい、そうして初めて江戸という存在がわかる。
結局一度も江戸のにぎわいを見ずして片田舎に埋もれて死んだ人が多いのである。だからこそ江戸は別世界の都の意味をもっていたのだ。この距離感で都は都でありえたのだ。今はあまりにも簡単に行けるからその都の存在価値がなくなったのである。とにかく遠い所はそこがなんであれ憧れの地となる。なぜ真野の萱原がただ萱原がなびいている処が面影にまで見る憧れの地だったかわからないのは昔の距離感がないから、奈良から見たらこの陸奥は決して行けない辺境だったからである。そこはなんであれ憧れの地となるのだ。外国も同じである。そこはあまりにも遠いから憧れの地となっていたのだ。飛行機で簡単に行けるとなるとその憧れの地としての価値が薄れるのである。
鄙(ひな)は日がなへるで、日の力が衰えるとなるがこれは都の近い所が鄙だった。つまり都から歩いて出ればすぐに日がなへる、日が暮れる、日が暮れて着くような処が鄙であり遠い所でなかったのだ。自分は町に棲んでいるがその町から離れて歩いて日が暮れる山とかが鄙である。つまり歩く感覚の距離感で生まれた言葉なのである。
御堂まで一里あまりの霞かな 漱石
御堂まで一里というのは歩くと遠いのである。だからこそ御堂が目印しになるのだ。一里塚もまたその歩く距離感の故に意味がある。今はこうした御堂であれなんであれ意味がない、歩いて旅すると必ず御堂に休むし雨宿りもする。そこで寝たりすることにもなる。ということは御堂は旅人にとっては都合のいい無銭の宿にもなったということである。時代劇で良く御堂に休み寝ている人がいるのはそのためである。
夕立や御堂に休み燕飛ぶ
こういう経験をするのが旅なのである。御堂とか街道の道しるべとかそうした昔生きていたものが意味をなくしたのは歩く旅ではなくなったからである。そこに人間の息づかいは感じられない、昔は地図がないとしたらどうしてその道を行ったのか、道しるべはかなり重要なものであった。それからなぜ馬子唄というように山中で歌を歌ったのかそれは山深い道でその居場所を知らせるために歌ったというのだ。つまりそれほど山というのはまた安全な道でもなかった。山の道など細いし暗いし怖いのである。白河の関所に出る所にはそれが残っていた。山賊もでた。そういう細い頼りない道が奥の細道だったのだ。今白河から福島から一関の道を行っても奥の細道など全然感じない、ただ自動車の騒音だけが頭に残るだけなのだ。奥の細道がいかに森や山に囲まれ奥深いものだったかそれは今の騒々しい道路や街の明かりを消してみてわかるのである。「寂けさや岩にしみ入る蝉の声」もまさにそうした静寂のわずかの細道をたどってきたからそれは余韻深いものとなるし平泉の金色堂も昔は全く別なものとして芭蕉には見えたのだ。つまり距離感を喪失したことは旅も喪失した。宿は旅の宿ではない、保養地、リゾ−ト的宿であって旅に休む場所ではない、だから今は逆に旅をすることは自転車で旅するとか何か普通の人にはやれない、手間暇と多大な労力のかかるものになってしまったのだ。
そもそも旅自体こうした歩くような労力をかけるから旅なのである。技術の進歩で得るものがあるのだが必ず失うものもあるのが人間社会である。今本当に旅するには自転車などでテントをもって旅するよりほかない、宿がないような所を行きそこでテントで一夜をすごす、苦しいがそういう旅が旅になる。草枕の旅である。しかし自転車だって一日に80キロも行くとしたらこれも早いのだ。だからたいがい必ず大きな街にでてくる。自転車すら早いからかつての歩いた人の旅を現代では偲ぶことはできないのだ。環境もまるで違っていた、舗装もされていな道を行っていたのだから全然違った印象をもって旅していたのである。
失われた旅の神秘性(2)
年たけてまた越ゆべしと思いきや命なりけり小夜の中山(西行)
旅路来て道は分かれぬ馬頭町その道行かず年も終わりぬ
栃木の那須高原を自転車で行ったとき、最後の方になって道は分かれて見るとそこは馬頭町への道だった。その辻には御堂があり道は四つに別れていた。なぜそこを覚えているかというと馬頭町という名前なのだ。馬頭町は馬頭観世音のことでありそれが名の由来なのだ。変わった名だと思ったから覚えているのだ。こうして旅で記憶に残るのは旅している証拠であり忘れた旅は旅としての意味がなくなってしまったのだ。自分の場合自動車がないから汽車で行く所はもう一回行けても自転車ではおそらく行けない、そこに行くということが一度きりとかその別れ道を去ったら二度とそこには行けないことになる。昔の旅はこういうことが多いのだ。だからそこを分かれ去りと言っている。分かれ去ってゆく、まさに昔の人の思いが残った言い方である。こういうことが自動車の世界ではわからない、つまりいつでも行けるじゃないかと考える、そこまで行くという貴重さとかがわからないのだ。芭蕉だってみちのくを旅したのは一回だけである。昔は大きな旅は一回くらいである。お伊勢参りでも一回くらいである。だからその旅は記念すべきものとなり各地にその記念として石碑が建っている。金比羅の碑とかがどこにでもあるのだ。現代はあまりに便利になりすぎて旅の神秘性、未知(道)なるものへ旅することが感覚的にない、いつでも行けるじゃないか、どこにでも行けるじゃないか、もう知らない町や村などないとなる。しかし旅には未知なるものへ向かう神秘性がないとつまらない、今やあまりにも情報化社会になって紹介されすぎるのだ。
そして外国ですらテレビで見たものを本で読んだものを確かめに行く旅になっている。旅に対する発見とかがないのだ。もちろん出会いというのもいつでもまた連絡できるからいつでも合いえる、出会いというものの貴重さを感じなくしてしまったのだ。便利過ぎること、知られすぎることは神秘性、未知なるものの喪失であり旅の期待を喪失させる。だから今では本当に旅する、未知なる旅をすることはかえって不便にすればするほど旅になる。でもこれをやるには大変な労力が必要となるのだ。自動車ではできない、歩くことや自転車でしたら大変な労力が必要なのだがそれしか本当の旅を味わうことはない、やはりこんなところにも人が住んでいるのかという神秘性である。こうした神秘性を感じるのは例えば中山道などではなく今は別な道になっている、そこは別に知られた町でも歴史的なものがなくても神秘的でありうる。旅はその行程のなかにありその行程の中で神秘性が生まれてくる。奥の細道は芭蕉のときはみちのくだったが他にもその行程の中で奥の細道はありうるのだ。汽車では線路は決まっているし自動車では早すぎてその奥の細道は発見されないのだ。過度な情報化は神秘性の欠如となりかえって旅を陳腐なものにする。観光地として紹介される所は旅に行くとしたら必ずしも今はいいとは限らない、今は旅ではなく保養である。旅することと保養は全然違う、観光地でもないありふれた所でも旅すれば神秘的であり興味をひくのである。
例えば西行の「年たけてまた越ゆべしと思いきや命なりけり小夜の中山」はこれはその当時の不便極まりない旅だからこの歌ができた。もう年になって小夜の中山を越えるのはこれで終わりだ。もう行けることはない、そういう決意から生まれた歌である。いつでも自動車で行ける旅ではないのだ。そこに行くことが命そのものだという感覚は今日ではありえないわからない、実際小夜の中山はどこかわからないがそこだというとこに行ってみたが実につまらんところなのだ。ありふれた所である。それはなぜそうなるのかまず汽車で下りてちょっと歩いただけの道だからである。そこまで行く長い行程が省かれているからつまらないのである。もちろんだからこの歌の重みも意味も理解できないのだ。汽車の旅も旅だがそれは歩いて旅するのとは全く別である。今確かに歩いて旅している人がみかけるが途中歩いているだけであとはバスや汽車にのっているのだ。結局どうしても便利な方に人は向いてしまう、だから現代では昔をまねて旅しても旅にならないのだ。昔は結局は追体験しようとしてもできない、そこに価値があるのだ。失われた昔はおそらく失われたもので最も貴重なものだった。その価値は二度と再現されないからである。その時代はその時代に生きてみてしかわからないものがある。それがわからなくなるのは環境がみんな違ってしまっているからなのだ。自動車や汽車の時間の感覚と歩く感覚はまるで違うのだ。だから現代は現実を旅するより瞑想の旅の方が豊かになれる。そこは想像の旅だから無限の神秘を旅することにもなる。私が地名を思い出して旅しているように想像の中の旅が豊かになっているという奇妙な世界が現代の錯綜した世界である。