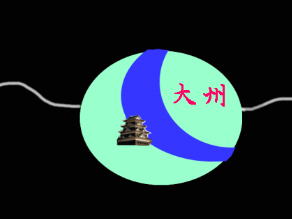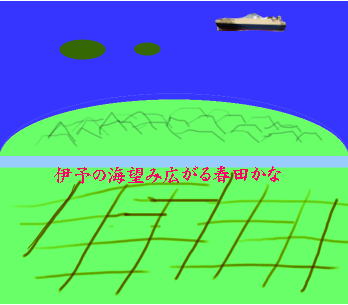詩情に満ちた春の伊予への道 (小林勇一)
(注意)名前のないのは自作の俳句と短歌です
●室津まで
四国全体が独特の風土と歴史を持ち詩情に満ちている。その険しい山と深い入江が地形的な特徴を成している。そこには忘れられたような鄙びた小さい古い港が隠れるようにあった。丘を越えて行ってもその港のあるところがわからなかった。そこに湾が広がっていたのだがそこから脇に入ってゆくと昔ながらの古い港がありそこに古い旅館が二軒あったのだ。本当に隠し港であり意外な場所だった。日本の港にはそういう小さい港が無数にあるのだ。
甲浦(かんのうら)奥に隠れて港かな春の夜一人旅人泊まる
10世紀前半、『土佐日記』よると、土佐守の任を終えた紀貫之は浦戸、奈半利(直利)、甲浦などを経て京都に帰還しており、また応仁二年(1468)、土佐幡多郡に下向するため堺を立った一条教房も大平氏の大船で甲浦から井ノ尻まで航行しており、甲浦が土佐中央部と畿内を結ぶ海路の要港であったことがわかる。浦戸-奈半利- 室津- 奈良志津(奈良師)は相当古い港である。ここからは木材を畿内に出していた。今も大坂-甲浦-高知のフェリ-が出るのはその名残か航路になりやすい要衝の港だったのである。
特に古いのは室津である。ここには津照寺があり船溜まりに面して塔が建っている。
「播磨風土記」によると、「風を防ぐこと室のごとし」なので室津と名ずけたとあります。
小島が唐荷島です。「 播磨国風土記 」によると、韓人の船が難破してその荷が漂
着したので韓荷島というとあります。
山部赤人が「辛荷島を通ずる時」に作った歌
玉藻刈る辛荷の島に島廻する鵜にしもあれや家思はざらむ
春の午後遍路に塔に韓荷島
「大名が泊まる本陣が六軒、脇(わき)本陣も兼ねた豪商の邸 宅、宿屋、置屋などが軒を連ね、『室津千軒』と呼ばれた。本陣が 六軒もあったのは、全国で箱根と室津ぐらいらしいですよ」
江戸時代参勤交代でこの港に寄ったのである。西国の各地の藩の紋を描いた船の旗が展示されている。ここにオランダのケッペルも寄って絵を残したところだから風光明媚な所なのだ。
http://www.muro-shimaya.jp/index.html
井原西鶴は「室津は遊女の発祥地」と書いています。
室津は遊女発祥の地ともいはれ、古代から江戸時代までにわたって繁栄を極めた。平安末期のころ、花漆といふ名の遊女は、唐人からもらった財宝を天皇に献上したところ、数々の宝を賜り、それをもとに室津に五つの寺を建てたといふ。
花漆ぬる人もなき今宵かな。室ありとても頼まれもせず 花漆
「同国室の泊につき船に小船一艘ちかつきたるこれ遊女かふねなりけり(中略)上人あはれみて(中略)ねんころにをしへ給けれは遊女随喜の涙をなかしけり」(『法然上人絵伝』巻34)
これは1207(承元1)年に法然が讃岐に赴く途中のエピソードで、友君という名の遊女を帰依させたことが記されている。のちの1228(安貞2)年、このエピソードの場となった地に法然の弟子である信寂を開山として建立されたのが浄運寺であったとされている。
ここにはいろいろな物語が残っているのはここがいかに栄えていた港かわかる。遊女が五つも寺を建てたなどということが普通ありえないからである。船が港に入ると最初に小舟で近づいて誘ったのが遊女だったのだ。ともかく港には遊女がつきものでありそれでこうした物語が残った。ここはオランダ人も朝鮮通信使も寄ったのだから国際的港でもあったのだ。ここに語り尽くせない物語が残った。
梅咲いて帯び買ふ室の遊女かな
朝霜や室の揚屋の納豆汁
蕪村は遊女と深くかかわった。ただこの遊女を今の売春婦と見るのは何か違うのだ。遊女という呼び名すら何か人間的で風流なものを感じてしまう。江戸時代はどこでも遊女が多かったし女性が職業を持てないから女性の職業として遊女があった。現代の売春婦は夜鷹のような下品な肉体だけを三文で売るような感覚に見えるのだ。例えば今の売春婦は交わっても肉体だけの交わりであり情緒も何もないのだ。江戸時代は遊女は社交の場でもあり何か違っていた。それでなければこんな情緒豊かな俳句を遊女の宿でできるわけがないのである。帯を買うということはここが豊かな証拠であり納豆汁は生活の実感のこもった句になっている。蕪村の句の不思議は芭蕉にはない庶民の実感のこもった生活感覚にあるのだ。現代の売春婦の方が文明が発達しても金だけで買われる殺伐としたものとなっているのはむしろ非人間的な世界になっているのだ。だから遊女が改悛するとかそんな物語など現代に生まれないのである。せいぜい宗教団体にとりこまれ終る。そこには情緒豊かな物語など生まれようがない、宗教団体には人間的な物語が生まれ余地がない、すべての人間が組織の中でロボット化され聞く話はヤラセであり作られた物語である。一人一人の対話などないから無数の人間の中で演出されるだけである。そこに一人の人間の誠は全く見られないのだ。一人の人間が存在しえないのだ。むしろ欠陥があっても一人の赤裸々な人間があれば救われる、それが全くない、全く作られた虚飾された人物を崇めているだけなのである。機械人間はいても人間は一人もいないし人間は存在しえない非情があるのだ。
つまり現代とは物語が生まれない不毛な非情の世界なのである。遊女というと有名な人は名前も残っている。一個の人間として名前が残されているのだ。名前が残っていることは個としての存在感があったということになる。今は必ず弱者は組織に入る。宗教団体でも組合でも組織に入ればかえって弱者は強者になる。現実差別された団体は社会で強者となり組織されない社会人に圧力をかける存在となるのだ。現代の弱者は必ずしも弱者ではない、組織化、団体化するから強者なのである。暴力団のように恐喝まがいのことすらするようになっているのだ。江戸時代は個々に遊女はいても遊女の団体は存在しないのだ。時代によってこうした春を売る女性も違ったものになるのだ。現代の景色そのものが非人間的であることも殺伐にしている。人間はビルの谷間に埋もれその物語もビルの谷間と騒音の中に埋もれてしまっているのだ。時折そのビルから悲鳴とともに飛び下りる人がいても瞬間的に無常のビルの谷間と騒音の中に消されるのである。遊女の謂われや墓が残っていること自体、何か人間的である。遊女の物語が多いのはそれだけ遊女が多かったことと遊女が当時存在感あるものだったのだ。遊女は隔離されたものではなくその土地や風景と一体となったものであり人間的なものとして許容されていたのである。
旅路寄り遊女の謂われ春の夕
吉原に限れば遊女の仕事の半分は酒の相手で、必ずしもすべての客に肉体的サービスを施したわけではないので現代の風俗嬢と比べれば少なくとも肉体的には楽だった。
http://home.interlink.or.jp/~5c33q4rw/nikki/2003_3.htm#8
江戸時代は明治以降からの時代感覚ではわかりにくい世界となっている。もちろんそこには悲惨な苦海に身を投じたかという見方もあるが遊女の世界は当時の社交の世界であり必ずしも体だけで交わる世界ではない。蕪村もそうである。体を求めたのではなく社交の場として利用する所だったのである。そこにはだからやさしい眼差しがあったのだ。
●宇和卯之町から大州へ
四国の景色で一番感動したのは宇和島から法華峠を脇道にそれた海岸線だった。その海岸線は入江はかなり奥まで入りこんでいる。春の雪が宇和島の鬼が城山をまだおおっている。宇和島は伊達藩のものが移住してきたので縁ある所だった。桑折という姓は桑折郡から移住した人達の姓である。桑折は郡であり郡山(こおりやま)というのもそうである。桑折郡は伊達の支配下にあり相馬藩とも隣り合っていた。桑折という姓は相馬にも鹿島町にもありなじみの姓である。
宇和島城への古びた石段にはなんともいえぬ情緒がしみついていた。
春寒し宇和島にきて老二人石段おりて落椿見ゆ
入江があり後ろに険しい鬼が城山がそびえている風景も東北には見慣れないものであった。宇和島は四方が山に閉ざされている。法華峠は凄い坂の峠でありトンネルもつづきあそこを自転車で行くのは容易ではない、トンネルは自転車の場合危険なことがある。歩道がないと音が反響して怖いのである。古いトンネルは歩道がない場合があるから怖いのだ。あの峠を行くず海岸に出たのは正解だった。旅をするときは電車だと鉄路にそって行く他ないが自転車だと道を選べるから景色のいい見晴らしのいい方に行けるのである。その海岸線にそって行ったのだが山が険しく迫っていてこの山を越えるのが一苦労だった。実際にこうした山陰にある港は背後がこのような急峻な山だとすると生活の糧は海からしかえられない、これも山の陰の隠されてある港だった。狩浜とあるのは鹿や猪を山で狩りしていた人達が海に出て海の魚を狩りするところから狩浜と名付けられたのだ。水夫をカコという時、鹿子にもあてられる。狩りをする鹿と関係していたのである。鹿を狩りするものが海で魚をとるようになったのである。
この坂を夕暮れにやっと越えた、夕陽がかがやき険しい山を見ると月がでていた。そして入江が奥深く入りこんでいた。四国の景色は山が高く入江が深く変化に富んでいる。だから鯨の碑があったが鯨はこの入江に入ってきたりしてその鯨をとったのである。鯨見の丘とかもある。鯨は「一頭捕ったら七村潤う」ほど大きな恵みだったのだ。日本は山が多い、その山を根拠にして最初の生活があり平地はやがて田畑となり海に生活は拡大して山幸、海幸の恵み豊かな日本となったのである。
鶯の鳴くや夕陽の没りゆきて山に月かな入江の深しも
港古り入江に山や春の月
この卯之町に出る景色は実に変化に富んでいた。私が卯之町に着いたのは夜だった。なんとか国道そいのホテルを見つけて泊まったがここがなんの情緒もない宿だった。途中夜歩いている遍路装束の若者がいたが休みを利用して歩いている人だった。休みを利用してちょっとだけ歩いている遍路もいるがこれは何かにわか遍路であり遍路のまねごとをしている。今は遍路のまねごとといえばみんなそうかもしれないが年配の人は一カ月も歩いている人がいるからこれらはそれなりに現代では歩く旅しているのである。一カ月も現代で歩くということはやはり大きな体験であり旅をしている。本当の遍路は行き倒れが多かったのだからそれ以上に深刻だった。旅になるのは自転車までであり車だと移動にしかならないから旅することはかえって今は大変なのである。
今回の旅の俳句のテ-マは春田だった。四国は山が険しく入江深く平地が少ない、でも何か穏やかなのである。春田に春の日がさして卯之町は盆地でありそこを遍路が朝の旧道を歩いていたのでそのあとから歩いてゆく、金銅杖で歩くの様になっているのだ。江戸時代の街道を行く旅人は広重の浮世絵になったように人間が歩く姿に感動すること自体いかに人間的なものが奪われてしまった文明世界かわかる。一歩一歩大地を踏みしめて歩く姿はなんとも頼もしいのである。これが人間の原型の姿なのだ。原生人間は歩いていたのだ。ただ車でひっきりなしに行く国道を歩いていると何か様にならない、車によって人間が邪魔なように見えてしまうのである。国道とかは車が主人であり人間が主人ではないのだ。今の文明自体が機械とかビルとか物が主人であり人間が主人になっていない、人間はそうした物の付属品なのである。人間が歩いて旅する姿には人間的情緒が自ずとかもしだされてゆく、車が通って行ってもそこには人間を感じることがない、車という物体を感じても人間を感じることがないのだ。車が人間を非人間化したことをあまり言う人もいないが根本的に車社会は便利でも人間の情を奪ってしまったことは確かなのである。人間が人間でいることが周囲の環境とマッチして調和することが自然本来の姿なのである。動物はどうしたって都会のビル谷間に不似合になるのは本来草原で草を食ったり森で生活していたものだからだ。人間も本来は自然とマッチして生きていた時、それ自体一つの絵であり美しいものであったのだ。モンゴルのゲルで暮らしている人々は外から見るとそうである。文明の中に暮らす人間そのものが歪んだいびつな存在である。今や人間は何かいびつでないと不具でないと正常でないようにさえなっている。インドとか中国ではわざわざ同情をひくために手足を切ったりまでして不具になっているという、それと同じように文明人は自らを不具にして俺はこのように不具なんだから権利を主張するというまでなっているのだ。文明人が別にミラ-とか上野霄里氏のような天才的巨人でなくても常識人でさえおかしなものと見えるはずなのだ。その一番象徴的なことが歩くことすら奪われた人間の姿にあることでもわかるのである。ともかく歩いてみないと遍路のことはそもそもわからない、鳥坂峠が山の中にありあの山道を歩いてみて昔の遍路の心細さがわかる。
卯之町というと卯之町には、シーボルトの弟子である二宮敬作の住居跡がある。二宮敬作は天保四年(1833)から安政三年(1856)までこの地で蘭方医として開業していた。二宮敬作はシーボルトから娘のイネ(伊篤)の養育を任され、一時期イネも卯之町に起居していた。二宮敬作住居跡のすぐ傍の路地を曲がると高野長英の隠れ家跡がある。高野長英は陸奥国水沢の人。高野長英も二宮敬作とともに鳴滝塾にてシーボルト門下で蘭学を学んだ。のち蛮社の獄と呼ばれる弾圧事件で投獄されたが、牢舎の火災に乗じて脱走し、宇和島藩に匿われた。一時期宇和島城下にも住んだが、追手から逃れるために卯之町に移り住んだ。
当時蘭学は武士とか知識階級にかなり教養として広まっていたのだ。その蘭学を基礎にして英学が起こり明治維新が達成された。江戸時代には様々な日本の歴史の集積があり明治維新もありえたのである。その一つが出島を通じてそれなりに西欧の文化が入ってきていたのである。ここは訪ねなかったので失敗だった。自転車だと先を急ぐ傾向がある。距離をかせがないと行けないから先を急ぐのである。江戸時代の歩きもかなり早朝に発っているのもわかる。卯之町から昔だったら山の中の鳥坂峠を越えるのだが一応峠を越えて大州にでた。大洲の第一印象は山の中に平地が広がっている、山に閉ざされた世界に広がっている春田の平地で大きな川が流れそこに城があった。大州は大津であり実際は海を意識した名だったとするが川の岸の大きな州がその名の起こりに思えた。ここからは海が見えないので海が意識されなかった。宇和島も実際は山の盆地に作られず海を意識して海側に作られたというのも四国では内陸の盆地より常に海が交通の要となるから海を意識していたのである。自転車で峠を越えて大洲に入るのと電車で大洲に入るのでは全然違った印象を持つのである。大洲にもいろいろな歴史があるが早くから先進文化を取り入れたところでもあった。
最近出した上野霄里氏の「新土佐日記」にしぐれという松山の名菓のことがでている。
晩秋や 菓子は「志ぐれ」や 伊予訛り 野村 博
しぐれというと山頭火がこだわったテ-マだったが歩いて旅した最後の人が山頭火であった。それ以後歩く旅人は消えた。今は歩いても歩いた旅にならない、車社会によって歩くというのが様にならなくなったからだ。山頭火までは木賃宿などもあり歩く旅ができたのである。そもそも自動車騒音社会の中で時雨を感じる感性すら奪われている。時雨を感じるにはかなりの繊細な感覚が必要でありその静寂な環境が破壊されれば時雨を感じえない、自然への日本人の微妙な感覚も失われているのだ。日本語の乱れも明らかに文明化現象とともに起こっていることでもわかる。訛りがなくなったのも地方の文化の消失なのだ。三重県の女性と北京であったが大坂弁のように聞こえたので大坂の人かと思ったが三重県だという、大阪弁のようでも三重県とか他も微妙にアクセントなどが違っているのだ。それが地方の文化であり文化の出会いがあり旅する面白さなのである。西の方が訛りを出して話す力にたけているし商人の伝統がある。東北はどうしても寡黙になってしまうから商売には向いていない、東北とは一面宗教的哲学的修養の場に向いているのだ。騒音社会の中で沈黙の世界であるべきなのだ。全部が商業や工業化して一様化することが文化ではない、様々な地方性があって文化がありバランスが保たれる。地域性を活かすことが第一である。宗教哲学、そんなもので飯が食えるかとなるが長い眼で見ればそれが独自のものとなり観光客をひきつけそこから波及する経済効果はそれなりにでてくるのである。どこに行っても東京と同じだとなれば個性なき人間が価値内容に存在価値がなくなってしまうのだ。
大洲藩江戸屋敷の秘宝菓子として広く愛されていた菓子を初代八太郎翁が志保町本店にて独自のものとして商いをはじめ、その後代々にわたり改良し、大洲地方独特の菓子として120年、日々研鑽を重ねています。
志ぐれは、江戸家中の秘法菓子として知られ、参勤交代の節、製法を伝授され、現代迄伝承、其の後、先輩達の御指導を受け、日夜研鑽努力し、製造秘法により、昔ながらの風味を失う事なく、現代好みに仕上げし品。
志ぐれという菓子がどうしてできたのかそこにもすでに長い物語がある。江戸で作られたとなると江戸からもたらされた。参勤交代の節、製法を伝授されたとなると参勤交代を通じて文化が伝えられた。江戸とのかかわりはやはり大きかった。
長いものぞな
まさき(松前)のかづら
蔓は松前に
葉は松山へ
花はお江戸の城で咲く
これは松山に残っている行商女の即興の歌と司馬遼太郎の「街道を行く」にでている。松前でとれたもの葉は松山へそれが江戸まで通じて江戸で花咲くというのも江戸とのつながりまで発展している当時の経済を唄で表したのである。志ぐれという菓子もそうである。これは逆に江戸からもたらされた。江戸からもたらされたという時、松山には高島屋とか三越とか東京に本店がある百貨店がある。これも東京から地方へもたらされた。江戸時代は大阪や京都の店が江戸に開かれたのである。双方向に文化の交流があったのである。
南蛮貿易をしていた頃、松山のお殿様が南蛮菓子からヒントを得て、餡子を入れることを考案したそうです。ポルトガルから言葉とともに入ってきたお菓子として有名なものは、カステラやコンペイトウ、カラメル、ボーロなどですが、タルト(トルテ)もどうやらそうらしいです。
タルトというのは南蛮菓子の影響があったというからこの辺は様々な文化の影響があったことがわかる。一方東北では江戸時代でもミカンさえ入っていない、茨城まで入っても東北までは入っていないからミカンさえ食えない貧しさがあった。ただ江戸には米を商品作物としてし供給していたのである。仙台米というのは有名だったからだ。西は歴史の地層は幾重にも重なっている。だから探ればいろいろなものが見えてくるし書くことも多くなる。
大洲から内子に行った。ここは?で栄えたというし輸出までしていた。春の山をバックにまるで浮世絵の町並みだった。四国は山が険しいのだが海がとりかこみ海岸は高知から離れると穏やかで温和な海になる。伊予はまさに一段と温和になっている。高知から峠を越えて坂本龍馬が大洲にも来た。高知は荒々しい風景でありそこから坂本龍馬のような志士が脱藩して明治維新を成したというのも地理と地形から考察すると躍動する人間の物語として現れてくる。歴史には地理と地形の考察が欠かせないのである。それは汽車とか車で行くとわかりにくくなる。今回折り畳み自転車で電車を利用したがそれなりに走ったのでこれだけのものが書けたのである。もし電車だけだったら四国の遍路のことは見えてこない、少なくても四国では昔のように歩くか自転車かの旅をしないとだめなことがわかる。一部分でも歩くなり自転車にするとこれだけのものが浮かんでくるのだ。
重信川、砥部焼、大洲、卯之町等へ旅していく。「伊予人の気風は南へ下るにつれてのびやかになる」と。司馬遼太郎が言っているがまさにそうだった。瀬戸内海の伊予の海は高知側とか崖がそそりたつ風景とは違っていて温和このうえないのだ。宇和島では春の雪が降ったから結構寒い場所であることがわかった。一方伊予は温和でありその春の海に向かって地蔵がその海を見て置かれていたのもほほえまし四国ならではの風景だった。
電車おり遍路見送る春の昼
伊予の海望み広がる春田かな
遍路の魅力(文明を離れ人間臭いものを求める旅)