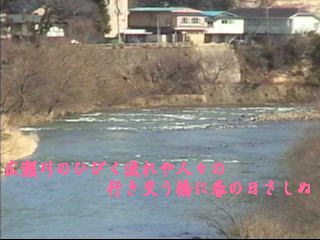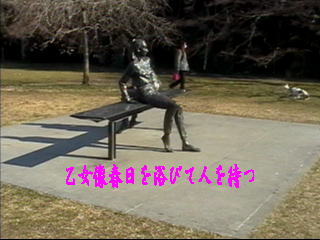仙台編(エッセイ俳句短歌など)(小林勇一)
時事問題に書いたものを集めて新しい「夏たちぬ仙台」を加える。
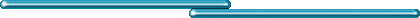
仙台のベストりアンデッキ
定禅寺通り
 夏たちぬ仙台
夏たちぬ仙台
春の広瀬川
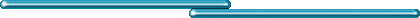
仙台のペデストリアンデッキ

何カ月かぶりに仙台に行った、ペデストリアンデッキというのは高いから気持ちがいいのかもしれない、仙台には前は一週間に一回くらい行っていた。もちろん原町を基点にして電車が一時間おきに通っているのだから通っている人もいる。一時間十分くらいでつく。そんなに遠くはないが最近それほど魅力を感じなくなっていた。というのは本をほとんど買わなくなったからである。今日は東北関係の本を高いのを買った。みんなで一万以上買った。bookoffにいい古本があった。地域の本だったがこれをあとから買おうと思ってもう一回よったらなくなっていてがっかりした。地方からでた本でかなり貴重なのがある。地方の本は希少価値がある。なかなか売られていないからだ。そして思ったことは知識はあるとき仕入れないと永遠にそのことがわからずしまいになることがある。有名人の知識はどこにでもあるから接しやすいのだ。どこの本屋でも石原慎太郎の本は置いてある。その本自体みんながそんなに必要としているかどうかに関係なく置いてあるのだ。知識の場合は物と違い売れるから必要なものとは限らない、マイナ-ものこそ実際は必要な人にとってはあってほしいものであるから知識に関しては他の商売と同じにはならないからやはりインタ-ネットのような知識の共有を目指すのが理にかなっているのだ。ともかくある人にとって必要な知識は意外と探すのに苦労する。特に私の場合旅に明け暮れたからどうしてもその地域の情報が欲しいのだがある地域に関しての情報は本当にわかりにくいのだ。あとから調べるのにも苦労する、インタ-ネットで多少はに狭い地域の点の情報が入りやすくなったことは確かである。偶然青森の方を旅したときインタ-ネットで見たサイトは有効だった。
役屋の松というのがあり役屋というのは佐竹の殿様の狩猟の役をつとめる場だった。そこに松だけが忠節の証しのように残っていたのだ。それで見たこともないが想像して作った句がこれである。
一本の役屋の松や冬の暮(自作)
そんな松があったのかと感心したことや男鹿半島の気候は荒れやすく潮風の影響で紅葉にならないということが書いてあった、そして寒風山という名が心にしみたのである。三月で春はまだ遠く雪の世界だった。なぜここが寒風山という名がついたのかまさにここの気候条件にあったのだ。ナマハゲという祭りもあの荒い北の果の海ににあった祭りであった。何を意味しているのかわからないが北の寒々しい嵐の化身なのかもしれない、旅したとき実感して大事なのは地理感覚と気候である。これは体験の世界だからわかりにくいのだ。汽車の旅だと地理感覚はわからなくなる、坂をやっと上って隣の街に来たとかそうした地理感覚が欠落するのだ。
沖縄に7月の一番暑いときに行ったのであの猛暑を体験して沖縄がわかる。からからに喉がかわきそこに珊瑚の石垣の家がひっそりとその暑さをさけるように静まっている。そこにいかにも日に焼けた老人が氷水を売っていた。そこではいかに水が大事かわかる。井戸の水が枯れて波照間島では村がそっくり移動したりしている。今では水は大きな島から船ではなく水道管を海に通して水を運んでいる島もあった。船で運ぶとなるとこれも大変だった。飛島の話しでは魚などと交換に酒田から米を仕入れていた。これは物々交換だった。物々交換できな家がありそれらは酒田の米屋から借金して米を食べていた。米を食べることが島では簡単にできなかった。沖縄の旅でもそうだった。内地の米は米だけでオカズなくてもうまいんだよなと言っていた。沖縄の米は安い米を買うからうまくないのだ。沖縄では前は田んぼが結構あったが今はなくなっている。内地ですら減反なんだから米を作っても金にはならないから果物を作るようになっているのだろう。
こうしたちょっとした知識というか学問的なことでもなく人々の生活実感を知らないとまるでその地域のことがわからずしまいになってしまうのだ。それは旅したかいもないことになる。こういうことをちょっと旅したくらいでは聞き出せない、それで民俗学者聞き調べたものが役に立つのだ。つまりあの飛島に行ってもやけに小さい島だなくらいしか印象として残らないのだ。そこにアメリカ人の観光客が一人できていたが外人だったら余計にわからない、というよりまるっきりあの島についてはわからずじまいになる。私が外国旅行したときがそうだったようにまるでそこが何なのかわからずじまいになるのが多かったのだ。一人の人間に例えるなら必ずその人の生い立ちがあり過去があり現在がある、それを知ることがその人を語る礼儀なようにその土地についても同じなのである。
仙台はそれほど特徴がない街である。森の都といっても多少街路樹が緑でもそれほど緑があるわけでもない、広瀬川があり青葉城があるから自然と歴史はあるがそれほど歴史ある街とはいえない、前は良く広瀬川辺りまで歩いていた。青葉通りも歩いていたが今はほとんどそこまでも行かない、駅前だけで買い物だけだから用を足して終わりである。都会自体通りに街の中の小さい商店街には足を運ばず駅前の大きなデパ-トだけで用をすませてしまうようになる。大きな都会でも人が集中するところとしない所に別れてしまうのかもしれない、商店街の不便は一軒一軒出たり入ったりすることにある。それ自体が不便になってしまったのだ。一カ所になんでも集まると買い物は便利だからだ。特に外から来るものにはそうなってしまうのだ。
これは物だけではないのだ。情報もそうである。インタ-ネットでどれだけ調べられるか新本か古本買ったが全然違ったものがきたりつまらないものだったりほとんど効果なかったので今は買わない、知っているものはいいが全く立ち読みできないものは当て外れなものが来るのが多かった。つまり情報の摂取方法はランダムに興味あるもの拾い読みしたり関連づけたりすることが必要でありそれは一冊の本ではない本の一部のペ-ジにある場合が多いのだ。とするとインタ-ネットのペ-ジを検索する方法はそれにあたるがインタ-ネットの情報はある関連したものがまとまってあるわけではないから無駄が多すぎるのだ。本は立ち読みが絶対必要でありそれなくし本は買いないのだ。また一方効率的情報の集め方に本のペ-ジを拾い読みすることが必要なのだ。それは本の全文検索にあたる。そうなると一冊の本自体今は高価だから関連した情報を集めることはできないのである。
私が今回買いそこねた地域の本がそうだった。この本の問題はもしその本がないとしたら永遠にその知識をその人の体験を知らずに終わってしまうことなのである。そういう知識や人の体験談はかなりある。なぜかというとこれまで出したいい情報は本は古本とかに膨大にありそれはもはや集められないし知り得ない情報になっている。そんなに買いないしわからないのである。だからインタ-ネット時代、著作権というのは何か不都合なのである。これまで本にするには大変な労力がかかりコストが高すぎた。本を作り流通させるのに7、8割りががかかり一割が印税として作者の手に入るだけだった。ところがインタ-ネットになったら8割りかかった本作りや流通のコストは無料になる。としたらもっと安く流通してもいいはずだが以前として古本などにいいものがありそれは高かったり多すぎて知られずに終わるのが多いのである。インタ-ネットのいい点はこうしてし日記のようにすぐに体験したことを書けることである。
仙台のペデストリアンデッキ
仙台のペデストリアンデッキを人々の歩む
新緑の樹の風にそよぎ乙女の髪も風にそよぐ
初夏の日ざしが明るくふりそそぎ
若いエネルギ-がここに満ちるように
東北新幹線がそのスマ-トな車体を見せる
新しいデバ-トもできてそこに入る
沖縄の特産点店でマンゴ-の黒砂糖を買う
何カ月かぶりに都会の風にふれる
カ-ネ-ションの花が街角にかざられ
人々の行き来も盛んである
新しい本と古い本を手にとり買い
新しい知識を仕入れる
街もまた一つの生き物であろう
仙台から東北の四方に交通が伸びる
古代の多賀城が基点のように
すでに壺の碑(つぼのいしぶみ)に靺鞨国が視界にあり
伊達政宗の視界はさらに遠くヨ-ロッパまで到達していた
そのような雄図がいかに生まれしや
政宗の親書をたずさえてバチカンに日本の侍が
秀吉の命令で九州の名護屋城から朝鮮征伐に
家康とも渡り合う戦国武将の視野の広さであろうか
広瀬川の流れの瀬音、反る青葉城の石垣
仙台より商人も各地に広がる
わが町にも仙台屋とか多々あるはそのため
燕が飛び交い街はまた装いを新たにする
ここも若きものの学都でもある
物であれ情報であれ知識であれ技術であれ
それが集まる所が都である
人は都で視野を広くして発想を豊かにする
それが都会の役割である


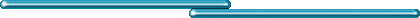
定禅寺通り
定禅寺通りに行ってのは何年かぶりだった。なぜここまで来なくなったのか、ここが駅からだと歩いて遠いからだ。今は仙台は駅前で買い物は用が足せる。本でもパソコンでもたいがい用はたせる。そしてもう一つはその他の日用品は郊外にある。大きな郊外のショピングモ-ルとか大駐車場のある所に車で行く、このように商店街自体が買い物とか生活の場から抜け落ちてしまった。定禅寺通りとあるようにここには禅宗の寺がありそれが名の起こりとなっている。ケヤキ並木が美しく通りには落葉が散っている。その落葉を踏んで人々が行き交う、この通りに面して喫茶店があり大きな窓がありその窓にもたれて落葉を踏んで行き交う人を見ていた。その喫茶店はなくなり安い喫茶店ができたが通りに面していても前のような気分は味わいない、この通りで二〇年も喫茶店をしているというのがホ-ムペ-ジで紹介されていた、それは二階にあり二階からのながめるのである。私は喫茶店が好きだった。学生時代から喫茶店に入るのが好きだった。音楽を聞くのもいいし何より私にとって喫茶店はもの思いにふける場所だった。だからいつも一人だったし私には恋人とか人と話する場ではなかった。いつも一人で物思いにふける場所だった。性格的なものもあるが喫茶店は一人で利用する場だった。特に旅行したときも必ず喫茶店による。そこで詩を書いたりしていたから必ず必要なものだった。ただ今になると喫茶店は高いから余り入らない、定禅寺通りの喫茶店は場所がいい、商店街になると見えるのは店だけであり味気ない、ここには自然がある。四季の自然がある。ア-ケ-ドの商店街より自然を取り入れた商店街の方が歩いて気持ちいいのである。折り畳み自転車でも走っていて気持ちいいのである。ス-パ-とかデパ-トとかにはこうした自然を取り入れることはできない、そこが一つの問題である。
広瀬川のせせらぎの音
春、街路樹が芽吹き
夏、青葉に風がそよぎ
若い人々がその風を受けて歩む
今はしんみりと落葉の通り
かつて大きな窓にもたれて
落葉踏む行き交う人々を見ていた
しかし歳月は流れもはや
その喫茶店は消えていた
ただすべては思い出となってゆく
・・・・・・・・・・・
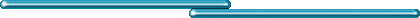
夏たちぬ仙台
夏たちぬ仙台
夏たちぬ
新緑の広瀬川にそい
その影涼しも
流れに憩う水鳥の
羽つくろいしてなごみぬ
その岸辺藤棚のよろしも
我は街の通りにい出ぬ
新緑に風そよぎ
新しきビルは建ちにき
伝統の学舎も古りて
学生や少女の歩む
古本を我は買いぬ
伊達政宗の雄図ははるか
秀吉と争い欧州にも
その青葉城の石垣の反り
広瀬川の早瀬のひびき
喜々として燕飛ぶかも
みちのくの都にあれ
我が青春は去りしも
青春はまたここに蘇り
若き等とともに未来に向かわむ
みちのくの都に再び夏はたちぬ
仙台に折り畳み自転車で長町でおりて行ったらすぐに広瀬川についた。意外と近いし長町にはおりたことなかった。電車は距離感をわからなくする。仙台に行くまでに阿武隈川や名取川などがありその過程が旅なんだがそれが省かれるから仙台に行ってもつまらないとなる。この折り畳み自転車はそういう点便利だ。これは例えば平泉に行くとする、ところが平泉の中尊寺辺りしか観光しないのが普通である。でも一歩はなれて例えば北上川にそい土手を自転車で走ったりするとそこの景色が全然違ったものに見えてくる。自転車で街に入るのと電車で街に入るのと感じが全然違ったものになる。今回長町から広瀬川に出て広瀬川そいを行き青葉城のたもとに出て街の通りを走った。これが歩きだったらできないが自転車だと簡単に行けるのだ。
伊達政宗は東北ではまれなる英傑である。それを四国のホ-ムレス遍路にあい再確認したことは面白かった。つまり秀吉がいなかったら伊達政宗が全国制覇していたかもしれないということなのだ。それほど伊達政宗は戦国時代大きな存在だったのである。そのことを四国の観音寺の公園でホ-ムレスと話したことの不思議だった。あの人は子供時代二本松で暮らしていたとか歴史のことを話できる人だった。歴史はその土地に行ってみると自ずからわかることがある。四国からみると大坂は近いのだから四国にとって大坂の存在は大きいのである。東北にとって鎌倉の存在が大きかったと同じである。その場所によって歴史の見方は大きく変わってしまうのである。九州でも沖縄でもそこに住んでみて日本を見るのと東北から北海道からみるのとはまるで違ったものになるのだ。地理と歴史は一体なのだから旅をして実地にその地を踏まないとわからないのである。頭でなくてその足で歩いて歴史はわかるのだ。電車や車やバスなどこうした便利なものは使うと歴史の感覚を養いない、なぜなら陸地は連続してつづいているのものでありその大地の連続性の感覚が途中で寸断されたりして連続的なものとして意識されなくなるからだ。
今回の目的は折り畳み自転車のBD1を見るためだった。これもわからなかったのだがインタ-ネットなどで調べた結果わかった。これが一番人気がありこれは最高峰の自転車なのだ。18インチでも長距離も行ける性能がある。これは見ただけで凄い自転車だということがわかった。このドイツ製の自転車は世界でも人気があり売れるというのがわかる。これを置いてあるのは仙台くらいでありそういう点買い物には困る。あとの電気製品はどこでも今は置いてある。自転車は置いてない、部品とか付属品も置いていないがわかれば通販で買える。通販で買おうとしたがあとの整備などが問題なので買えなかった。この次行ったらやはりBD1を買おう決めた。この自転車については有名だからインタ-ネットで相当な知識を得た。ただ自分の弱点はメカに弱いから何か壊れたとき困るので通販に躊躇していたことなのだ。どうも現代の道具は使ってみないとわからない、ブリジストンのトランジットは後ろが18インチで前が16インチだがこれが自転車を不安定にしているのだ。軽さを追及した点ではいいがこの点走りにくくしている。自転車みんな完全な満足あるものはない、どこか不満になってしまう。
デジカメにしてもそうだ。富士フィルムのFINPIXF700は電源を入れるのはスライド式になっていて面倒なのである。大きさも結構大きいから携帯性にいいといえなかったし画素数が多くてもたいして変わらない映りだったし不満な点が大きかった。それに一部壊れたの意外だった。悪いものではないがもっと小型のものでボタン式で電源を入れられるのがいいのだ。ポケットに入るくらいのがいいのだ。そういうものも富士フィルムのであった。今の商品選びまず使ってみないとわからないから困るのだ。だから値段にこだわると失敗する。DVDレコダ-にしてもそうだ。最初からハ-ドディスクついているものを買った方が使いやすいし得だった。DVD-RAW形式のを買って失敗だった。書き換えできても高いものだったからこれを買うのに二万くらい使ってしまったからだ。ともかくBD1という商品の選択は間違いない、これだけがぬきんでているからだ。選択の余地がないということは買う方にとっても楽なのである。
やはり街とはそもそも市から始まったのだから買い物に行くところだった。BD1は東北で置いてあるところは仙台くらいしかないかもしれない、ただこれもかなり知られたものだからそれなりに今は置いてあるのか、都会にしか売ってないものがあれば都会の価値がでてくる。今では田舎で売ってないものは通販でも買える。
矢矧の市に 沓買ひにかむ 沓買はば線鞋の 細底を買へ
さし履きて 上裳とり著て 宮路通はむ (催馬楽)
平安時代にもすでに市に通い靴を買っていたことは驚きである。これは中国から流行してきた最先端の鞋だったというのも驚きである.この気持ちは今でも同じだった.つまりBD1のドイツ製の自転車がこの中国製の靴なのである。唐物といえばいい品物のことだが今や逆転して日本製がいいものなのだから時代は変われば品物の価値も変わる。
インタ-ネット時代は情報化時代というときどういうことなのか、広瀬川沿いには有名な詩碑があった。
広瀬川− 萩原朔太郎
広瀬川白く流れたり
時さればみな幻想は消えゆかん。
われの生涯(らいふ)を釣らんとして
過去の日川辺に糸をたれしが
ああかの幸福は遠きにすぎさり
ちいさき魚は眼(め)にもとまらず。
これはインタ-ネットでわかったのだ。仙台でもこうしたことがわからない、広瀬川で羽つくろいししている水鳥がいて心がなごんだ。街でもこうした自然があると人の心がなごむ。東京の公園ですらそこに鳩がいて餌をやると気持ちがいいのだ。広瀬川があるから仙台も自然はある。東京でも隅田川があるところは自然があるから気持ちがいいのだ。街はまた絶えず変貌をとげる。新しいビルがたち新しいものが流入してくる。その変わりかたも早い。それがまた一つの魅力なのだが仙台でも長町から名取とかでると田んぼになる。東北で一番大きな都市でもそうなのである。だから人間的だとなる。
田舎駅のホ-ムに電車を待っていたらタンポポの綿毛がとび蟻もでてきて歩みはじめた。ホ-ムに待つ時間があるし蟻を歩むのを見ている時間もある。自然がまだ観察できる時間がある。ところが尼崎の電車の事故では一分一秒を争う熾烈な時間競争をしていた。これは全く人間的ではない、そういう世界に生きている人間は時間も空間も奪われてただ機械につめこまれる会社人間のロボットと化しているのだ。異常な時間感覚のなかに生活していたのだがそれが当たり前となり異常が異常であることに気づいていなかったのである。
タンポポの綿毛飛びくるホ-ムかな
蟻歩むホ-ムに待てる時間かな
広瀬川の緑陰行きて静かなれ学舎のわきに古本を買う
水鳥の広瀬川にはつくろい心なごみぬ春の昼かな
街路樹の新緑にそよぐ風吹かれ若者歩む仙台の街
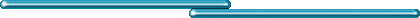
春の仙台-PHOTO
街に出て人と交わるや春の雲
乙女像春日を浴びて人を待つ
広瀬川のひびく流れや人々の行き交う橋に春の日さしぬ
残雪の泉が岳見ゆ河畔には乙女の像あり我がよりぬかも
夏たちぬ仙台